平成27年度 洛友会東京支部行事予定および報告
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・・・・・・・・ |
平成27年6月28日(日) 於 学士会館210号室 |
|
|||||
|
・・・・・・・・ |
平成27年11月10日(火)18:30〜20:30 於 学士会館 講演者:米原 伸 様 京都大学 大学院生命科学研究科 高次遺伝情報学分野 教授 演題:細胞の死が支える生体の生と機能 |
|
|||||
|
・・・・・・・・ |
平成28年3月25日(金) 情報通信研究機構(NICT)訪問と江戸東京たてもの園散策 |
|
|||||
|
・・・・・・・・ |
囲碁会、麻雀会、 ゴルフ会、 洛謡会、 テニス会 |
|
|||||
|
・・・・・・・・ |
おぼろ会、京極会、
洛粋会、洛談会、洛笑会 |
|
|||||
|
・・・・・・・・ |
第1回 幹事会(開催済み): 平成27年5月17日(日) 於 学士会館 第2回 幹事会(必要に応じて): 未定 (参考)次年度幹事会 平成28年5月頃 於 学士会館(予定) |
|
|||||
|
|
|||||||
|
・・・・・・・・ |
平成28年2月13日(土) 於 京都大学東京オフィス(品川) 講演者:浜口 友一 様 明治大学国際総合研究所フェロー 演題:企業変革のリーダーシップと社員力 |
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
1.支部総会・本部総会・支部講演会・懇親会
開催日
平成27年6月28日(日)
場所
学士会館210号室
[住所] 〒101-8459東京都千代田区神田錦町3-28
[電話] 03(3292)5936
[アクセス] 地下鉄都営三田線 都営新宿線 東京メトロ半蔵門線
神保町駅(A9出 口)徒歩1分
[URL] http://www.gakushikaikan.co.jp/access/
スケジュール
14:00〜14:55 洛友会東京支部総会
15:00〜15:55 洛友会本部総会
16:00〜17:00 講演会
講師:京都大学宇宙総合学研究ユニット・特任教授、一般財団法人リモートセンシング技術センター参与
中野 不二男 先生
17:00〜18:30 懇親会
会費:
会員5,000円 同伴者2,000円
但し卒業5年以下(H22年学部卒以降)の会員は無料、
また、平成27年4月1日現在で75歳以上の会員は3,000円
報告:
平成27年6月28日(日)、学士会館にて、東京支部総会、本部総会、講演会及び懇親会を開催しました。本部より長尾会長、荒木幹事長、高岡幹事を初め多数の来賓をお招きし、82名の参加をいただき、例年にも増しての盛会となりました。
【支部総会】
支部総会は安田支部長の司会により、午後2時に始まりました。
古屋総務幹事より平成26年度行事・活動報告[第一号議案]があり、支部総会後の講演会では、京都大学元総長の松本紘様をお招きし、大変興味深いご講演をいただけたこと、その後の懇親会では長尾会長のご挨拶を初めとして、米寿、喜寿を迎えられた方の一言や、「琵琶湖周航の歌」合唱で大盛況であったこと、秋の講演会では「宇宙工学と宇宙政策の世界 〜探検する宇宙、危機あふれる宇宙、生活に密着した宇宙〜」と題し、京都大学生存圏研究所・同大学院工学研究科電気工学専攻(協力講座)の山川宏教授からご研究がご紹介されたこと、春の見学会では東京都三鷹市の国立天文台を訪問し、天文台の先端装置や基盤技術、4次元デジタル宇宙シアターの見学など充実した内容であったこと、3月の若手勉強会では株式会社アークの中野哲浩様をお招きして「エンジニア出身経営者の製造企業改革の軌跡」と題して、ご講演をいただいたこと、などの紹介がありました。また、5つの趣味の会、6つの拡大クラス会の状況について報告があり、拍手をもって承認されました。
続けて、平成26年度決算報告および監査報告[第二号議案]があり、ほぼ予算計画通りの決算となったことが田邉会計幹事より説明されました。この決算内容に対し、小森監事から適正に会計処理され決算報告に記載されているとの監査報告が行われ、決算報告および監査報告は拍手をもって承認されました。
次に、平成27年度の役員/幹事[第三号議案]の提案が行われました。平成27年度の新役員/新幹事は、支部長 成宮憲一(S49卒)、副支部長 小森光修(S50卒)、監事 真崎 義孝(S51卒) 、総務幹事 田邉義孝(H8卒)、会計幹事 福原忠行(H9卒)、庶務幹事 浅井孝浩(H7卒)、若手勉強会幹事 古屋裕規(H7卒)の7名となりました。また、空席だった学年幹事を5名追加したこと、評議員では複数名からご辞退をいただいたこと、拡大クラス会では五九洛会とみとおし会が活動終了となったことをご報告し、拍手をもって承認されました。

安田支部長 成宮新支部長
安田支部長から退任の挨拶がありました。「グローバルな形で洛友会がお役に立てるように、若手の人にも参加してもらうことを目的として企画に取り組んできました結果、少しずつ多くの若手に参加をしてもらえるようになってきました。更に多くの若手に参加して頂いて、全体として洛友会の活動が活発になるように本部の副会長として引き続きサポートさせていただきたい。講演会・見学会については、この1年「宇宙」にテーマを絞って企画してきましたが、今後も活動を活発化していただきたい」との話がありました。
引き続き、成宮新支部長から就任の挨拶がありました。「若手の横の連携・つながりを作って、洛友会に参加していただくことを考えています。特に20代の人に参加してもらえるようにしていきたい。今年の秋の講演会では、京都大学大学院生命科学研究科の米原伸教授に「生命科学」というテーマで講演をお願いしています。若手交流会では、経営者の方から話を聞きたいという若手のご要望にお応えし、元NTTデータ社長の浜口友一様(S42卒)に講演をお願いしています。」との話がありました。
次に、田邉新総務幹事から、平成27年度行事・活動計画[第四号議案]について説明を行いました。例年通り、秋の講演会、若手交流会、春の見学会などの行事、拡大クラス会・趣味の会を実施すると共に、登録会員数向上、若手活性化施策、全学同窓会活動との連携を検討していくこと、などが説明され、拍手をもって承認されました。更に、平成27年度予算計画[第五号議案]が説明され、拍手をもって承認されました。
その後、平成27年度に米寿・喜寿を迎えられた方々(米寿1名、喜寿5名)に対し、大きな拍手と共に会場より祝意が表されました。
以上をもって、平成26年度洛友会東京支部総会は閉会となりました。
【講演会】
「宇宙・人文学への招待」と題して、京都大学・宇宙総合学研究ユニット特任教授の中野不二男先生からご講演いただきました。
ご講演内容
3月31日までJAXAにいたが、松本元総長からいろいろやってみないかということで、宇宙人文学を始めました。宇宙人文学は宇宙人の文学ではなく、宇宙の技術と人文学を融合させるのが目的で、日本の古典文学や古文書などの記述を衛星からのデータで解明してくいく、700kmの距離から古事記を探るというテーマです。日本の古典文学や古文書などの記述を、JAXAが上げたALOSから得られた地形データから分析します。
地球観測衛星であるALOS(陸域観測技術衛星「だいち」)で取得される観測データは電波の波長の違いによって見え方が変わります。RESTOCというシステムがあると、これらの観測データを基に立体地図を書くことができます。
日本書紀・古事記には災害に対する事績が書かれています。古事記は、天武天皇が天皇の系譜と世の中の出来事を、神話として構成するように稗田阿礼に伝えたものです。「島になる おのころじま」は「海に漂う国々の」 「潮が固まって国になる」と記述されています。そこに出てくる「淡路のしま」「伊予のしま」は淡路島と四国ですが、おのころじまだけが実在が不明です。そこで、立体地図を作って、水面を上昇させて島を推定しました。古事記に出てくる難波津、住吉津、紀水門(きのみなと)は海の近くにあったはずです。住吉津は海外から来た船の一時係留港でした。難波津は、現在の大阪の地形で海水面をバーチャルに上昇させたときの海岸付近にあたる高麗橋と、安政大地震の被災絵図面で大津波が最も奥深くまで達した地点と、3つの時代を超えて一致することが分かりました。 紀水門は四国に行くための出発地です。和歌浦にある玉津島神社の周辺の水面を下げる(周辺の地形を隆起させる)と、沖合いが島だらけになりました。これらの島々が古事記にある「様々な国」にあたるのではないでしょうか。。684年の地震が日本書紀に非常に細かく書かれています。11年間に17回の地震があり、この時、地面が隆起して、淡路島の南側の中央構造線上に沼島ができた可能性があり、これが「おのころ島」ではないかと思います。
現在の地形を傾けたり回転させたり、水面を上昇させたりすると昔の地形を再現できる可能性があります。例えば、更級日記にある記述を基に、江ノ島付近の海面を、貝塚の場所を基に水面の位置を変えると、昔の地形は相当北まで海が広がっていたと予想しています。ここまでは、標高データを基に調査したものです。ALOSの近赤外データを使うと植物のクロロフィルを調べることが出来ます。これを使えば植物の発育状況が分かります。
高校生のテーマとしていろいろな研究をしてもらっています。日本全国にある縄文時代の貝塚の高度が違うので、そこから昔の海水面を推定したり、羽柴秀吉の備中高松城の城攻めが本当にできるかを確認したり、「これより下に家を建てるな」という碑を基にどのような津波の浸水になるかをシミュレートすることが出来ました。
このように衛星から得られる情報で様々な現象をシミュレートすることが可能となります。
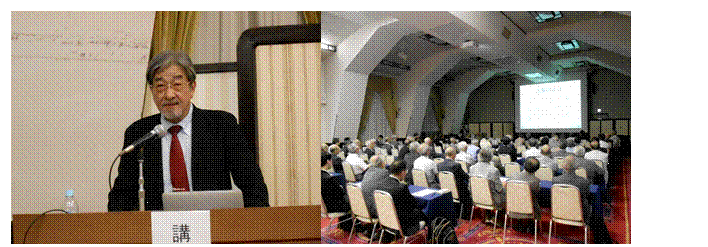
中野 不二男 先生 講演の様子
【懇親会】
午後5時より、恒例の懇親会に移りました。懇親会は、成宮新支部長の開会のご挨拶のあと、長尾会長のご挨拶と乾杯のご発声で始まり、例年にも増して、幅広い年齢層にわたる多彩な参加者の交流の場となりました。会員の方々の活発な意見交換が行われました。趣味の会幹事の方から各会のご紹介、米寿・喜寿を迎えられた方から一言を頂いた後、福原新会計幹事の音頭により、恒例の「洛友会の歌」及び「琵琶湖周航の歌」を合唱しました。 最後に、小森新副支部長の中締めにより、午後18時30分に散会となりました。
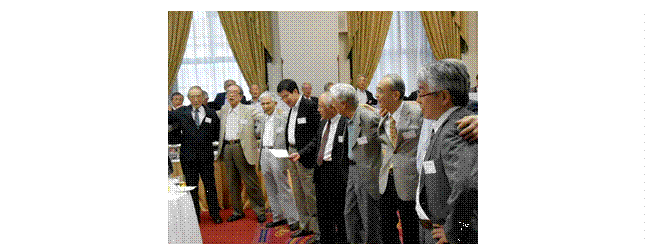
琵琶湖周航の歌斉唱
[報告] 洛友会 東京支部 会計幹事 福原忠行(H09年卒)
2.秋の講演会・懇親会
開催日
平成27年11月10日(火) 18:30〜20:30
場所
学士会館320号室
[住所] 〒101-8459東 京都千代田区神田錦町3-28
[電話] 03(3292)5936
[アクセス] 地下鉄都営三田線 都営新宿線 東京メトロ半蔵門線
神保町駅(A9出口)徒歩30秒
[URL] http://www.gakushikaikan.co.jp/access/
講演者
京都大学 大学院生命科学研究科 高次遺伝情報学分野 教授
米原 伸 様
演題
細胞の死が支える生体の生と機能
スケジュール
18:30〜19:30 講演会
19:30〜20:30 懇親会
会費
講演会会費 2,000円(懇親会込・ご同伴者同額)
報告
平成27年度秋の講演会は、11月10日(火曜日)18時30分から学士会館にて開催されました。
今年は、京都大学生命科学研究科高次遺伝情報学分野教授の米原伸様から「細胞の死が支える生体の生と機能」〜自爆するための細胞表層レセプターの発見から多様なプログラム細胞死の解析について〜と題して講演を頂きました。
今回の話題は、生体の発生、細胞の分化の話であるということで、最近注目されている、iPS細胞、ES細胞の違いについて説明を頂きました。ES細胞は、受精卵を分化することで作られた万能細胞(多能性幹細胞)でありそれを試験管内で分化、培養することで、神経細胞、表皮、心臓、筋肉、内臓などあらゆる組織をつくることができるものです。
一方、iPS細胞は、人体から採取した体細胞に、ノーベル医学賞を受賞された山中先生の発見された「山中因子と呼ばれる」多能性誘導因子を与え、それを培養することで生成された万能細胞(多能性幹細胞)であります。これも同様に試験管内で分化、培養され、あらゆる組織が作られるという意味で、
iPS細胞もES細胞もその後の過程は同じですが、生成する元が、受精卵か、人体等から採取された細胞か、による違いです。 ただ、ローマカトリックは、受精卵を使用する、ES細胞を認めないのに比べ、iPS細胞は倫理的に認めるものとなっています。別の観点からは、ES細胞は、まったく同じ個体を作らないのに対し、iPS細胞は、まったく同じ遺伝子の人間を、理論的には生成することができるという点があります。
本日のテーマは、この細胞の分化の過程であり、分化の過程には、細胞の死が大きく関わっていること、生体の維持にも細胞の死が必要なこと、ガンの発生は、正常な細胞死ができないことによるものが多いこと、などを説明いただきました。
まず、受精卵は分化して、生体に変化していきますが、その分化の過程で細胞が死ぬことで、体の組織が構成されます。例えば手指ははじめ水かき状の被膜があり、指間の被膜細胞が死んで縮退し、手指が形成されるそうです。これらの細胞死により、臓器の大きさや機能は、細胞の増殖と死のバランスで一定に保たれていますし、正常な体にも発生するがん細胞も、生体内で発生時のいずれかの段階で自らを破壊するように指令を受けており、この細胞が死ぬことで体内に生成したがん細胞は死滅して正常な状態が保たれています。この死滅が正常に行われない場合が、所謂がん、です。本来発生しない場合に細胞死が発生することによる疾患もあり、AIDS、免疫不全症、神経疾患、貧血、などが該当します。これらの細胞死は、アポトーシス、ネクローシスという、2つのタイプの細胞死に分類され、アポトーシス、は、ギリシャ語で「枯れ葉が落ちる」という意味だそうです。
細胞死が、定まったタイミングで必ず起きることを発見したのは、2002年、ノーベル医学生理学賞を受賞した「線虫を用いた組織発生と細胞死の遺伝学的研究」の研究者3名(ブレナー、サルストン、フロイス)によるものです。線虫の分化の過程を観察すると、線虫は1090個の体細胞で出来ていますが、その受精卵の分化の過程で、うち、131個の細胞が必ず決まった時期に死ぬことが確認されたことで、細胞死が組織形成に大きな役割があることが分かりました。
この細胞死の発生のメカニズムは分子レベルで現在解明されてきており、細胞死を誘引するタンパク質や酵素の働きも、解明されてきています。マウスを使った実験でもその現象が説明でき、遺伝子によりある細胞死ができないマウスは、正常な個体が発生しない等の確認がされてきているとのことです。
一方、ガンの発生も、細胞死がかかわることは先に述べた通りですが、最近の研究では、P53と呼ばれる遺伝子が細胞死を正常に働かせることで、ガンの発生を抑制することなどが分かってきているとの研究成果なども説明されました。


その後、質疑応答の後、懇親会が行われました。成宮支部長の乾杯の発声では、米原教授は、成宮支部長と、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学と、同じ経緯を辿られた、1年後輩で、憲ちゃん、伸ちゃんと呼び合う仲であることなどが披露され、仲の良さがにじみ出ていました。その後、米原教授を囲んで会員との意見交換が和やかに行われました。
今回の講演は、細胞の死というものが、生体の維持にどれだけ大切なものか、今まで、全く気にしていなかった我々にも、改めて感じさせて頂ける良い機会となりました。
[報告]洛友会 東京支部 総務幹事 田邉 義孝(H08年卒)
3.見学会・旅行会
開催日 平成28年3月25日(金)
訪問先 情報通信研究機構(NICT)訪問と江戸東京たてもの園散策
会費 5,000円(同伴者の方も同額)
参加者数 22名
報告
桜も咲き始めた3月25日(金)、恒例の春の見学会を開催いたしました。本年の見学は、東京都小金井市の情報通信研究機構を訪れました。22名の方にご参加をいただきました。
皆様のご協力の下、JR新宿駅を定刻に出発し、10時00分に情報通信研究機構に到着いたしました。

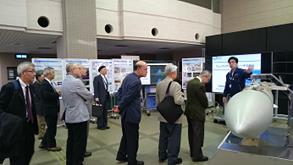
高橋幸雄研究所長のご挨拶 フェーズドアレイ気象レーダの見学
現地では、今回の見学にご対応いただく情報通信研究機構のお出迎えを受け、サイバーセキュリティ研究所のシアターにて、高橋幸雄研究所長から歓迎のご挨拶をいただきました。引き続き、インシデント分析センターで研究されている、ネットワークを流れるサイバー攻撃を検出するシステムnicterにより、各国から日本へ送信される大量のウィルス通信を可視化する技術を見学しました。世界地図上のあらゆる国から日本に向けて攻撃されている様子は圧巻で、サイバー攻撃の恐ろしさを感じました。
ここからは2班に分かれて、竜巻やゲリラ豪雨を予測するためのフェーズドアレイ気象レーダの研究、正確な時間を計測する日本標準時の研究、光デバイスを形成するための光通信基盤技術のためのクリーンルームを見学しました。特に日本標準時の高度化技術に関しては、東大と共同で研究を進めており、50mの高度差のために相対性理論の影響で極微小の時間のずれが発生したとの逸話には驚かされました。


日本標準時の見学 光通信基盤技術の見学


集合写真 昼食会場の様子
情報通信研究機構の見学後、季節割烹 弥左衛門に移動し、昼食をとりました。御膳を堪能しながら、話題に事欠くことなく、楽しい時間を過ごしました。昼食後は、バスに乗って小金井公園に移動し、江戸東京たてもの園を見学しました。高橋是清邸や三井八郎右衞門邸などの他、千と千尋の神隠しの参考となった建物ゾーンでは建物だけでなく、昭和の商品レプリカに懐かしさを感じずにはいられませんでした。
その後、バスにて新宿駅まで戻りました。参加者皆様のご協力のお蔭で、定刻通りの解散となりました。
今回の見学にあたり、事前のご準備、当日ご対応いただきました、富田理事をはじめとする情報通信研究機構の皆様に感謝申し上げます。


江戸東京たてもの園の見学 千と千尋の神隠しの参考となった建物
[報告]会計幹事 福原 忠行(H09卒)
4. 趣味の会
趣味の会では、会員を募集しています。興味のある方は、各会の幹事メールアドレスまで、直接ご連絡下さい。
|
|
幹事 |
幹事メールアドレス |
|
|
(1)囲 碁会 |
喜多村 滋 (S36卒)、向井 利典(S41卒) |
囲碁会行事案内 |
|
|
(2)麻 雀会 |
舩山 眞弘(S39修卒) |
麻雀会行事案内 |
|
|
(3)ゴ ルフ会 |
古澤 久具(S35卒)、山澤 穣(S38卒)、田崎 信(S44卒) |
ゴルフ会行事案内 |
|
|
(4)洛 謡会 |
村上 薫 (S36卒) |
洛謡会行事案内 |
|
|
(5)テ ニス会 |
山内 英樹(S44卒)、 田中 喜男(S44卒) 、成松 洋(S46卒) |
テニス会行事案内 |
5. 拡大クラス会
|
名称 |
平成27年度 幹事 |
|
|
|
(1)おぼろ会[S21〜S24卒] |
舟 田 正男(S24卒)、門脇 誉雄 (S24卒) |
おぼろ会行事案内 |
|
|
(2)京極会[S35〜S39卒] |
藤江恂治 (S37卒) |
京極会行事案内 |
|
|
(3)洛粋会[S40〜S44卒] |
洛粋会行事案内 |
||
|
(4)洛談会[S45〜S49卒] |
逢坂 福信(S45卒)、嶋谷 吉治(S49卒) |
洛談会行事案内 |
|
|
(5)洛笑会[S50〜S54卒] |
川原崎 雅敏 (S50卒) |
洛談会行事案内 |
|
6. 幹事会
日時: 平成27年5月17日(土) 12:00〜16:00
場所: 学士会館本館(2階203会議室)
住所:〒101-8459 東京都千代田区神田錦 町3−28
電話:03(3292)5936
交通:地下鉄都営三田線または都営新宿線または営団半蔵門線
神保町駅(A9出口)徒歩30秒
http://www.gakushikaikan.co.jp/access/
主な議事内容:
(1)平成26年度行事・活動報告
承認
(2)平成26年度決算報告および監査報告
承認
(3)平成27年度の役員/評議員/幹事
承認
(4)平成27年度行事・活動計画
承認
(5)平成27年度予算計画
承認
(6)その他
・拡大クラス会五九洛会、みとおし会は、平成26年度を持って活動を終了した旨が報告された。
・評議員と学年幹事について議論され、今後の評議員の選出については、基本的には支部長経験者を評議員とすることで会則が昨年変更されていることが確認された。
・若手活性化施策として、若手勉強会参加者からのアンケート結果に基づき、開催時期や名称(若手勉強会)の変更について議論された。
・平成21年度卒業移行の学年幹事の選出を進め、新たに5名の方に学年幹事を引き受けていただいた旨が確認された。
[報告] 洛友会 東京支部 H26年度庶務幹事 浅井孝浩(H07年卒)
開催日:
平成28年2月13日(土)
場所:京都大学東京オフィス(品川)
[住所] 〒108-6027 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟27階
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/tokyo-office/about/access.htm
講演者:
明治大学国際総合研究所フェロー
浜口 友一 様
講演題目:
企業変革のリーダーシップと社員力
参加者数:
31名
スケジュール:
14:00〜15:30 講演会
15:30〜16:30 懇親会
会費:
講演会:無料
懇親会:500円
報告:
平成28年2月13日(土)、 京都大学東京オフィス会議室におきまして、明治大学国際総合研究所フェロー・元NTTデータ代表取締役社長の浜口友一様をお招きし、「企業変革のリーダーシップと社員力」と題するご講演をいただきました。若手会員から要望の高かった企業経営に関する講演ということで、例年にも増して若手会員からの期待度が高く、平成年度卒業者の参加者が八割を占めました。
ご講演は、浜口さんご自身のご経験からの学びのまとめから始まりました。学べないものはない:好ましくない経験も反面教師とする、適者生存:環境に適合すべく、常に変わっていく、原点に帰る:本質(お客様にいい商品・サービスを提供する、利益は後からついてくる)を見失わない、ピンチはチャンス:常にポジティブに考える、など、経営の場面での具体例を交えてご説明いただきました。
続いて、NTTデータの改革の歴史を説明いただきました。1988年の会社発足にタスクフォースメンバーとして関わられて以降、組織のフラット化、人事改革、間接部門スリム化、管理会計導入、組合一本化など、様々な改革を推し進められてきました。社長になられた2003年以降は、成長の鈍化・マーケットの変化に加え、部門間コミュニケーションの劣化、間接部門の増大など、いわゆる「大企業病」という更なる課題に直面される中、更に改革を加速されました。
「お客様満足度No.1」を最大の目標に掲げ、中期経営方針を立てられた中、まず、事業面でポートフォリオの入れ替えを行われました。国内市場の鈍化を踏まえてグローバル化を進める一方、ITサービスのコモディティ化に対しては、自社のコアコンピタンスを重視し、あえて高級路線を推進されました。経営体制としては、いち早く執行役員制を導入すると共に、取締役会を2時間制とするなど、経営のスピード化を図られました。配当性向を高め、株主総会の運営を改善し、株主重視の姿勢も整えられました。販売管理費については、R&D経費は企業の成長を支えるための「税金」と考える、販売促進費は使う前提で努力し、安易に削減しない、との自論をお話頂きました。なにより、このふたつを削減すると、やりたいことができなくなり、社員に元気がなくなってしまうとのことです。
並行して、大企業病の徴候が見られていた組織文化の改革に、2つの方向からアプローチされました。ひとつめの「ビジョンの策定と浸透」では、30代半ばの若手社員を含めたタスクフォースを立ち上げ、グループビジョンを策定されました。更に、その浸透のため、国技館でのビジョンキックオフ、社員と幹部がビジョンについて語り合うビッググループセッションを実施されました。その結果、社内のビジョンに対する共鳴度が大きく向上したとのことです。ふたつめの「現場力向上」では、NEXTリーダー育成会を立ち上げ、現場力の鍵となるリーダーを育成されました。更に、行動改革WGを作成され、ここから社内SNSやテレワークなど、現場力向上の様々な施策が実現されてきたとのことです。
最後に、ハーバード大ビジネススクールのジョン・コッター教授の企業変革のフレームワークを紹介され、浜口さまの進められてきた改革は、こちらによく即していたと振り返られました。
大企業経営者から、実際の経験に基づく企業経営に関する様々なお話を伺うことができ、普段、企業経営を身近に感じることができない大半の若手会員にとり、大変有意義な講演となりました。質疑応答でも多彩な質問が寄せられ、講演会は大盛況のうちに終了しました。
講演会終了後、成宮支部長の乾杯の音頭により、懇親会を行いました。浜口様を取り囲む若手会員は途切れることがなく、企業経営に関する活発な意見交換がなされました。又、フレッシュで和やかな雰囲気の中、若手会員相互の交流も活発に行われました。


[報告] 若手勉強会幹事 古屋 裕規(H07卒)
以 上