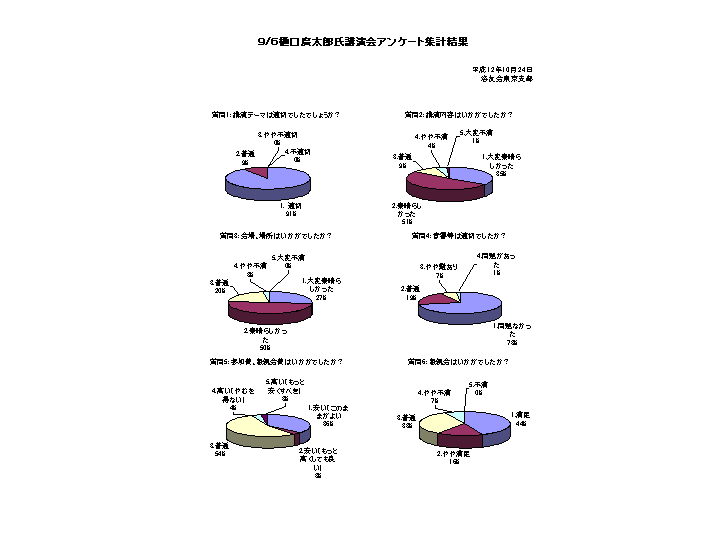|
1.総会 ・・・・・・・・・ |
平成12年5月28日(日) 於 八芳園 なお2001年は6月16日(土)に開催します! |
|
2.旅行会 ・・・・・・・ |
|
|
3.見学会 ・・・・・・・ |
|
|
4.講演会 ・・・・・・・ |
|
|
5.趣味の会 ・・・・・ |
|
|
6.グループ活動 ・・ |
平成12年5月28日(日)に、例年通り目黒の八芳園にて、東京支部の評議員会、支部総会を実施しました。
昭和9年卒業の大先輩から平成11年卒まで、総勢66名の会員の参加が有り、本部からは近藤文治会長、池上文夫副会長、教室からは詫間 菫教授、奥村浩士教授を来賓としてお迎えしました。
評議員会は廣支部長による挨拶で始まり、名簿発行、各種行事が無事実施できたことへの御礼が述べられました。続いて平成11年度の行事、予算・決算等の報告及び平成12年度予算案説明及び次期役員候補紹介が濱野総務幹事より行われ、承認されました。
支部総会では、廣支部長の挨拶に始まり、昨年度一年、会員の皆様の支援により活発な活動が行えたことへの御礼が述べられました。また今後予算制度も抜本的に改革されてゆくため、これらに備える必要がある点も指摘されました。続いて近藤文治会長(左下写真)のご挨拶をいただきました。昨年は電気教室100周年行事を向かえ、我々は100年の重みを考える機会を得たことが述べられました。また電気系教室のありかたが大きく変貌してゆく状況、同教室が新桂キャンパスに第一号として移転する点についてお話し頂きました。さらに今後とも活発な活動により、関西、東京両支部が洛友会の両翼を担って行って欲しいとの願いが述べられました。
その後、平成11年度の予算・決算報告等が審議、承認されました。引き続き平成12年度の新役員を選出し、川本新支部長より挨拶をいただきました。新支部長からは、本会を知的好奇心を満たせる良い意味での大人の紳士社交クラブであるよう、よい企画、よい会員を大切にし、特にソフト面での充実を図って行きたいゆきたいとの抱負が述べられました。続いて平成12年度の行事計画・予算案が審議、承認されました。その後、奥村教授から、情報学研究科設立に伴う、電気系教室の変革の概要、今後建設が予定されている桂キャンパスの移転計画、学生の就職の現状報告が行われました。先生には大変入り組んだ移転計画を、OHPを用いて大変わかりやすくご報告下さいました。その後平成11年度に米寿・喜寿を迎えられた方々(米寿8名、喜寿9名)のお祝いを行ない、出席されていた横山様(S10年卒)、原田様(S21年卒)に代表として、それぞれ米寿、喜寿お祝いの目録が手渡されました。
支部総会の後、恒例の懇親会(左写真)は廣前支部長、詫間教授のご挨拶の後、角新副支部長の乾杯で始まりました。あちこちで、久しぶりに再会した会員の方たちの話の輪があちこちで広がりました。また、米寿を迎えられた横山様、喜寿を向かえられた原田様に記念のスピーチを頂いたりと、和やかなひとときを過ごしました。最後は川本新支部長の〆で散会しました。
冬にさしかかろうとする12月2日(土)、洛友会東京支部の平成12年度旅行会(アクアライン(海ほたる)と房総半島)を開催致しました。
1 アクアライン(海ほたる)より太海フラワーパークへ
前日、東京では小雨がパラつき天候が心配されましたが、当日は快晴に恵まれ、しかも千葉房総方面では前日より気温が6度も高いとのこと。今年度は例年に比べ旅行会の開催が遅れ、寒さが気になっていましたが、この一言で一安心です。
集合時間の8時には全員揃ってさあ出発。さっそくアクアラインを通って海ほたるパーキングエリアで休憩、10時前だったため開いているお店は少なかったものの朝の空気を通して見る東京湾の景色は清清しいものでした。
この後バスに揺られ、房総海岸沿いの太海フラワーパークへ。車中今回のガイドさんはなんと昨年の洛友会東京支部の旅行会でお世話になったガイドさんと偶然にも同じ方であることが判明、何人かの方は記憶にあるとのことでした。フラワーパークでは初冬にもかかわらず多くの種類の花が咲いており、また海岸の散策においても房総の暖かさが実感されました。
2 みかん狩りと酒蔵見学
フラワーパークの後は昼食です。バスも迷いながら到着したのは合宿所の食堂風の場所。大丈夫かなあ?との心配をよそに出された魚料理の数々はさすがに海沿いだけあってどれも美味でした。特に”かわはぎ”の煮付けは最高でした。
(集合写真拡大149k)
さて満腹のお腹を抱えてのみかん狩りです。少々急斜面で足元が心配されましたが、皆さん斜面を登り食後にもかかわらず、さらにお腹いっぱい食べお土産も持って帰られました。
最後は小泉酒造での酒蔵見学及び各種日本酒の試飲。お酒好きの方はそれぞれお気に入りのお酒を買われ帰途につきました。途中、せっかく房総に来たのだからと干物屋さんに立ち寄りお土産を購入しました。再び海ほたるで夜景を楽しみ、午後7時過ぎ無事東京駅に到着し解散致しました。
ご参加頂きました皆様どうもありがとうございました。また旅行会の開催に協力頂いた多くの方々また”はとバス”の皆様に感謝いたします。今後とも楽しい企画をしてまいりますのでよろしくお願い致します。
洛友会 東京支部 会計幹事 小倉光裕(S57電子卒)
洛友会東京支部 見学会報告
|
|
朝は寒さを感じたものの、良く晴れ渡り、3月16日は絶好の行楽日和となりました。平成12年度の見学会は、75名の参加者を迎え、現在移動通信分野にて世界をリードするNTT
DoCoMoR&Dセンタ (神奈川県横須賀市)を訪問しました。 |
|
写真1 NTT DoCoMo R&D センタ前での集合写真 |
|
R&Dセンタでは、まずプレゼンテーションホールにて洛友会メンバでもある総務部の廣田 哲夫様が我々をお迎え下さり、同センタの沿革をご説明いただきました。本R&Dセンタはこれまで各地区に分散していた研究所機能をここYRPに集約させて98年より活動を開始されました。現在ではさらに研究機能拡充のため、隣接地にもう一棟のビルを建設中で、完成後は1000人規模の研究開発体制になるとのことでした。 |
|
|
写真2 プレゼンテーションホールにて |
見学は25名ずつ3班に分かれて行われました。マルチメディア評価室では、数多くの音響特性を実現できるよう工夫された空間であり、そこにて恐竜のコンピュータグラフィックスをはじめとする興味深い映像を楽しみました。
展示室では、これまでの移動通信の発展の系譜がわかるよう、端末を中心とする多くの製品が展示されていました。中でも本年5月から開始されるIMT-2000の試作開発設備も展示されており、2Mbit/sにて高品質画像を伝送する様子や、想定されるマルチメディア端末のモックアップが展示され、多くの人々の関心を引いていました。筆者にはすでに'70年の万国博覧会にて展示(使用?)されたとある今となっては大型の携帯電話器が印象深く感じられました。
その他には、想定される地震に備え免震構造を支える地下のダンパ(?)や車両も格納して測定可能な大型の電波無響室も訪問させていただきました。残念ながら電波無響室はたまたま実験中ということで入れませんでした。
丁寧な女性3名の案内も含め、総じて素晴らしくオーガナイズされた見学でした。受付前にはようこそ洛友会様のディスプレイも表示頂いておりました。
|
|
昼には場所を三崎港に移し、「三崎館本店」にてマグロ料理を楽しみました。三崎港はつとにマグロの水揚げで知られた港ですが、当地では普段は食べられない部分をも料理して出すとのことで、この日は刺身の他に皮とか胃袋とかが出されました。(かぶと焼きが有名ですが予算の関係上割愛しました)。食後は、三崎港周辺を散策し、思い思いに土産をみて購入しました。多くの方が冷凍マグロなどを購入しておられました。港には大きな魚市場があり、早朝には活発なセリが行われるのが想像できました。 |
|
写真3 三崎館本店にて昼食1(角副支部長の乾杯) |
|
|
帰路は京急三崎口を経由して横浜駅まで向かい、3時30分過ぎに東口に到着して無事解散いたしました。 |
|
|
写真4 三崎港でのマグロ昼食2 |
洛友会東京支部 総務幹事 大橋正良(S56電II卒)
ご質問、ご感想ございましたらohashi@kddlabs.co.jpまでお願いいたします。
<目次へ戻る>
洛友会東京支部平成12年度講演会
「21世紀、日本新生に向けて」
洛友会東京支部では、平成12年度講演会として、我ら京都大学の大先輩であるアサヒビール 相談役名誉会長樋口 廣太郎氏をお招きし、9月6日(水)、16時より東京丸の内 銀行倶楽部で開催しました。(樋口氏のプロフィールはこちら)
今回は、独立した講演会としては、東京支部初めての試みでしたが、会場をほぼ埋め尽くす160余名の参加を得、改めて人々の関心の高さを示しました。また経済学部の同窓会の方々や東京支部メンバのご友人の参加もいただきました。写真1 参加された方々と銀行倶楽部の様子
開会に際し、川本支部長より挨拶が行われ、樋口廣太郎氏の略歴の紹介、本講演会参加への感謝、また今後の洛友会活動への支援お願いなどが述べられました。
続いて樋口氏より1時間半に亘り講演が行われました。樋口氏は、大変わかりやすい言葉で、我々にこの10年で日本はなぜだめになっていったのか?ならば21世紀に日本を良くして行くために何が必要なのか?そして、良くするための具体的な提言の数々を、「民」の立場から明快にまた忌憚無くお示しいただきました。最後にはこれからも規制緩和が非常に重要であり、これを進めるためには私たちの考え方を変えて行く必要があると締めくくられました。(講演のサマリはこちら)
写真2 樋口廣太郎氏 講演の様子
17時50分より懇親会に移りました。再度川本支部長よりお言葉をいただいた後、廣前支部長より乾杯の御発声をいただき、一同アサヒスパードライで乾杯。その後樋口様を囲み談笑の時間を過ごしました。樋口様も多忙ながらできる限りの時間を割いて我々におつきあい下さいました。最後に池上副会長より締めのご挨拶を頂戴しました。
写真3 懇親会の様子
末筆になりますが、本講演会に際し、薄謝ながら快くご講演をお引き受け下さいました樋口様に厚く御礼申し上げます。また事務連絡などで大変お世話になりましたアサヒビール秘書室、福岡様に御礼申し上げます。樋口様ご紹介には藤江幹事(S37卒)に労をお取りいただきました。ここに感謝します。最後に受付業務に多大なご尽力を賜りました日立テレコムテクノロジーの皆様方に厚く御礼申し上げます。
なお講演資料の残部が僅少ございますので、実費(1000円、送料込み)でおわけします。必要な方は幹事までメールでお申し付け下さい。
洛友会 東京支部 総務幹事 大橋正良(S56電II卒)
ご質問、ご感想ございましたら、是非ohashi@kddlabs.co.jpまでお願いいたします。
相談役 名誉会長 樋 口 廣 太 郎 プロフィール
- 1926年 京都生まれ。 京都大学経済学部卒。
- 1946年 住友銀行に入行。 1973年 取締役。 1975年 常務取締役。
- 1979年 専務取締役。 1982年 副頭取に就任。
- 1986年にアサヒビール顧問から社長に就任。
翌年、日本初の辛口ビール「スーパードライ」を大ヒットさせ、ビール業界の流れを変える。
社長在任の6年間にアサヒビールは売上高3..1倍、ビール売上箱数3.6倍となり、業界第2位に躍進。(シェア9.6%から現在は43%強となり、ビール業界第1位となった。)- 市場の商品を新しくするため、古いビールを回収し、処分
- 最高の原料使用を促進するため、工場利益管理制度を廃止
- お客様からのマイナス情報を収集するため、マーケットレディを大量に配置
- 情報共有化のため、全体社長朝礼を実施
など従来のビール業界にはない革新的な経営手法を導入、活力溢れる企業体質を構築した。
以上
主な著書
- 『知にして愚』(祥伝社)
- 『樋口廣太郎の元気と勇気が出る仕事術』(オーエス出版社)
- 『樋口廣太郎の起業家に原点あり』(東洋経済新報社)
- 『前例がない。だからやる!』(実業之日本社刊)
- 『樋口廣太郎語録』(ソニー・マガジンズ)
- 『つきあい好きが道を開く』(日本経済新聞社)
- 『今こそ前へ』(共著・法研)
- 『明日を読むヒント』(読売新聞社)
- 『もう5センチ頭を下げて』(財界研究所)
- 『だいじょうぶ!必ず流れは変わる』(講談社)
- 『日本経済新聞 プロの読み方』(小学館文庫)
- 『一日一話』(PHP研究所)
- 『チャンスは貯金できない!』(三笠書房)
- 『日本経済「日の出」は近い』(共著 唐津一氏)(PHP出版)
- 『人材集』(講談社)
- 『まずは上座へ』(マガジンハウス)
- 『僕らは出来が悪かった!』(共著・財界研究所)
- 『IT時代・成功者の発想』(共著・PHP研究所)
- 『さぁ!明日を語ろう』(共著・フォレスト出版)
2000年7月現在
略 歴
生年月日 大正15年1月25日
- 1949年 3月 京都大学経済学部卒業
- 1949年 4月 株式会社住友銀行入行
同行 五反田支店長、秘書役、東京業務部長、東京業務第一部長、業務推進部長等を歴任- 1973年11月 同行 取締役
- 1975年12月 同行 常務取締役
- 1979年12月 同行 代表取締役専務取締役
- 1982年 9月 同行 代表取締役副頭取
- 1986年 1月 アサヒビール株式会社 顧問
- 1986年 3月 同社 代表取締役社長
- 1992年 9月 同社 代表取締役会長
- 1999年 1月 同社 取締役相談役 名誉会長
- 2000年 3月 同社 相談役 名誉会長(現職)
- 1999年 7月 財団法人 新国立劇場運営財団 理事長(現職)
- 2000年 3月 日本ナスダック協会 会長(現職)
公 職
- 1995年 5月 社団法人経済団体連合会 副会長
- 1998年 5月 経団連 自然保護協議会 会長(現職)
- 1999年 5月 経団連 評議員会 副議長(現職)
- 1994年11月 中央連合簡易保険加入者の会 会長(現職)
- 1995年 9月 通産省 輸入協議会 委員(現職)
- 1995年11月 大蔵省 財政制度審議会 委員(現職)
- 1997年 5月 総務庁 公務員制度調査会 委員(現職)
- 1998年 8月 経済戦略会議 議長、小渕内閣対応
- 1999年 3月 産業競争力会議 委員
- 1999年10月 民間資金等活用事業推進委員会 委員長(現職)
- 1998年 5月 財団法人 産業教育振興中央会 会長(現職)
- 1993年 5月 財団法人 日本スペイン協会 会長(現職)
- 1995年 3月 財団法人 日独協会 会長(現職)
- 1995年 6月 イタイリアにおける日本年推進委員会 委員長
- 1995年10月 財団法人 日伊協会 副会長(現職)
- 1997年 9月 「ドイツにおける日本年」実行委員会 委員長(現職)
- 2000年 1月 日本アメリカンフットボール協会 コミッショナー(現職)
- 2000年 3月 警察刷新会議 座長代理
- 2000年 4月 市町村合併推進会議 議長(現職)
- 2000年 7月 産業新生会議 委員(現職)、森内閣対応
以上
アンケート結果
今後の検討に資するためみなさんにアンケートをお願いしました。77名のご回答をいただきました(pdfは上をクリックください)。
樋口氏講演概要
(なお本文は総務幹事大橋が聞き取った内容から構成したのもので、樋口氏講演の意図を正確に言い表しているとは限りませんのでご承知下さい)
|
財政問題 |
・戦後より日本は一貫して「貯蓄」、「輸出」を奨励してきた。80年代日本は、国土に資源が少ないながらもLook East,Look Japanと言われるほどに成長した。一方、当時米国は「財政」、「貿易」の双子に赤字に苦しんでいたが、これを解決したのが、サミュエルソンが提案した減税政策である。減税によって米国の両赤字は次第に解決し、米国財政は、今後10年間は黒字が続くと見られている。 |
|
日本社会を良くするための提言 |
・社会が悪くなった大きな理由の一つは、日本社会が、あらゆる面で過度の平等、公平を重んじた護送船団方式に凝り固まってきた点にあり、今後は、(リスクをとって)努力した人が報われるようにしなければならない。 |
|
(1)囲碁会 |
幹事:渡辺 寿夫氏 (S32卒) |
|
(2)将棋会 |
幹事:伊藤 貞男氏 (S32卒)、三好 良一氏(S30卒) |
|
(3)麻雀会 |
幹事:中田 良知氏 (S38卒) |
|
(4)ゴルフ会 |
幹事:石黒 公 氏 (S40卒)、安原 碩人氏 (S33卒) |
|
(5)洛謡会 |
幹事:近藤 貞吉氏 (S28新卒) |
|
(6)テニス会 |
幹事:白庄司 昭氏 (S33卒)、武田 学氏(S41卒) |
|
(1)洛京会[S8〜S11卒] |
幹事:林 潔氏 (S10卒) |
|
(2)洛楽会[S12〜S16卒] |
幹事:永安 弘 氏 (S16.3卒)、河辺 一氏 (S16.3卒) |
|
(3)東友会[S17〜S20卒] |
幹事:松橋 達良氏(S17卒) |
|
(4)おぼろ会[S21〜S24卒] |
幹事:藤原 孝造 氏(S21卒) |
|
(5)五九洛会[S25〜S29卒] |
幹事:山中 卓氏 (S26卒) |
|
(6)みとおし会[S30〜S34卒] |
幹事:森安 正司氏(S34卒) |
|
(7)京極会[S35〜S39卒] |
幹事:幸野 眞士氏 (S35卒) |
|
(8)未定[S40〜S44卒] |
幹事:未定 |
以上