����23�N�x�@���F����x���s����
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�E�E�E�E�E�E�E�E |
����23�N6��25���i�y)�@���@�w�m��� 14:00�`14:55�@�����x������ 15:00�`15:55�@�{������ �@�@�@�@�@�@�@�@�u��ЊQ���_�@�ɍl�����w�ƎЉ�̕������v 17:00�`18:30�@���e�� |
|
|||||
|
�E�E�E�E�E�E�E�E |
����23�N11��29���i�j�@���@�w�m��ف@210���� 18:30�`19:30�@�u���� �u�t�F�Ɨ��s���@�l�@�����w�������@ ������X�[�p�[�R���s���[�^�J�����{�{�� �@�@�@�@�@�@�u�����F�P�O�y�^�t���b�v�X�̃X�[�p�[�R���s���[�^�u���v 19:30�`20:30�@���e�� |
|
|||||
|
�E�E�E�E�E�E�E�E |
����24�N3��3���i�y�j�@ �@�@�Ɨ��s���@�l�@�F���q���J���@�\�@���z�q��F���Z���^�[ �@�@���w��A���H |
|
|||||
|
�E�E�E�E�E�E�E�E |
|
||||||
|
�E�E�E�E�E�E�E�E |
|
||||||
|
�E�E�E�E�E�E�E�E |
��1����i�J�Íς݁j�F�@����23�N5��29���i���j�@���@�w�m��� ��2����i�K�v�ɉ����āj�F�@����23�N10�����@���@�w�m��� �i�Q�l�j���N�x������@����24�N5�����@���@�w�m��فi�\��j |
|
|||||
|
|
|||||||
|
�E�E�E�E�E�E�E�E |
H23�N�x���𗬉�A������i��芲����Ɠ����J�Áj���e1��J�ÁB |
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
�P�D�x������E�{������E�x���u����E���e��
�J�Ó�
����23�N6��25���i�y�j 14:00�`18:30
�ꏊ�@
�w�m���
[�Z��]�@�@ ��101-8459�����s���c��_�c�ђ�3-28
[�d�b]�@�@ 03(3292)5936
[�A�N�Z�X]�@�n���S�s�c�O�c�� �s�c�V�h�� �������g���������
�@�@�@�@�@�@�@�@ �_�ے��w�iA9�o���j�k��30�b
[URL] http://www.gakushikaikan.co.jp/info/access.html
�X�P�W���[��
14:00�`14:55�@�����x������
15:00�`15:55�@�{������
16:00�`16:50�@�����x���u����i���s��w�@���{�h �����j
�u��ЊQ���_�@�ɍl�����w�ƎЉ�̕������v
17:00�`18:30�@���e��
����F
���5,000�~�@������2,000�~
�A������5�N�ȉ��iH19�N�w�����ȍ~�j�̉���̕��͖����ł��B
���F
�@�����Q�R�N�U���Q�T���i�y�j�A�w�m��قɂē����x���̑���A�u����y�э��e����J�Â��܂����B�~�J�������v�킹�鏋�����ɂ�������炸�A�W�W���i�����x������V�R���j�̎Q�������������A��N�ǂ���̐���ƂȂ�܂����B
�x������͊��c���������̎i��ɂ��A�ߌ�Q���Ɉ��x�����ɂ�鈥�A�Ŏn�܂�܂����B
���x��������́A
�@ �����Q�Q�N�x�̊����Ɋւ��āA�H�̍u����ł��͂�Ԃ��̂i�`�w�`��������̍u�����P�R�V���̎Q���Ƃ�����������ɍs������B�܂��������ł͂m�s�s�h�R���̍����������A�C���h��TATA���ٗ����グ�Ƃ�����ϋ����[���e�[�}�ł̍u���ɑ��A�������Q�����������B�������Ȃ���A�k�Ђ̉e���ɂ��A�R���P�Q���ɊJ�×\��ł������P������w���s���ƁA���A���Ƃ܂����̎��̌𗬉������~���Ȃ������Ƃ���ώc�O�ł������B
�A ���F����x���̊����ɂ����ďd�v�ȓ_�͉�������ƌ������B��̉�A�g��N���X��Ȃ��������ɍs�����߂ɁA������m���A����i���d�v�ł���B�ŋ߂̓��[�������p���Ă��邪�A�A�h���X���ς��ȂǑΉ�������ɂȂ��Ă��Ă���B�������Ȃ���A��芲���̊����ɂ��A�ǂ��ɂ��i�߂Ă����B
�Ƃ̕�����܂����B

�܂��A�V�����N�x���}���āA������d�v�ł���ƔF�����Ă���A���̋@��Ɏ�����𐳎��ȉ�Ƃ��đg�D�����悤�Ǝv���Ƃ̒�Ă�����܂����B�����ŁA���N��芈�����̂��߂ɂ��s�͂��������������l�ցA����萷��Ȕ���Ŋ��ӂ̈ӂ�������܂����B
�Ō�ɁA�e���̋������h������悤�Ȕ��M�����Ă������Ƃ��̗v�A���̎h���Ɣ����Ƃ��}�b�`����Ɨ��F����傫�����W����ƍl���Ă���A��������x�����w�������肢�������A�Ƃ̂��b������܂����B
�����āA���c����������蕽���Q�Q�N�x�s���E�����m��ꍆ�c�ān������A�x������̍u����ł̓R�}�c��\�������⍪���O�l�A�H�̍u����ł́u�͂�Ԃ��v�̂i�`�w�`����~��Y���������������A���ɑ吷���ł��������ƁA�܂��A�k�З����ɗ\�肵�Ă������w��ɂ��ẮA���O�ɂi�`�w�`�̊W�̕��X�ɂ����������������ɂ�������炸�A���~�ƂȂ��Ă��܂������ƁA2���̎�����ł͂m�s�s�h�R���̍����l���C���h�̂��o���ɂ��ċM�d�ȍu�����������������ƁA�̏Љ����܂����B�܂���̉�A�g��N���X��̏ɂ��ĕ�����A���F����܂����B
���ɓI���v������蕽���Q�Q�N�x���Z����ъč��m��c�ān������A�\�Z�v��Ɣ�r���āA�H�̍u����̏o�Ȏ҂��������x�o�����������A���w����~�ƂȂ������ƁA���𗬉�ɂ��Ă͊����̓w�͂ɂ���R�X�g�ŊJ�Âł������Ƃɂ��x�o�������������Ƃ���������܂����B���̌��Z���e�ɑ��A���V�Ď�����͖��Ȃ��Ƃ̊č����s���A���Z����ъč��͖������F�ƂȂ�܂����B
�@
���������ĕ����Q�R�N�x�̖����^�]�c���^�����m��O���c�ān�̒�Ă��s���A����������ď��F����܂����B�����Q�R�N�x�̐V�����́A�x�����@�������i�r�S�T���j�A���x�����@���V�G�i�i�r�S�U���j�A�Ď��@�V���m�i�r�S�V���j�A���������@�I�꒼�l�i�g�O�S���j�A��v�����@����m���i�g�O�T���j�A���������@���c���V�i�g�O�S���j�̂U���ƂȂ�܂����B
�@�����đޔC�������O�x�������A�z�b�v�X�e�b�v�W�����v�ŁA�Ō�̃W�����v�ɂ����Đk�Ђł�肫��Ȃ������A�V�x�����̉����l�Ƀo�g���^�b�`���A��肻���˂��Ƃ��������Ă��炤�A�܂����ɑ�ϊ撣���Ă��炢���ӂ������A�Ƃ̂����A������܂����B
�����Ŏi��҂��I��V���������Ɍ��ƂȂ�A���������ĉ����V�x�������A�C�̂����A�����������܂����B�����x��������́A
�@
�k�Ђ������A�Ȋw�Z�p�ƎЉ�A�����A�l�Ƃ������ւ�荇���ɂ��Đ[���l����������B���{�����̋��݂ł���Ƃ���̈�v�c���ł���܂ł���Ă������A�Ђ��݂�����A���ꂩ��̓O���[�o���Ȗ��A���G���A���{�Љ�̐V�����t�F�[�Y�ɑ��Ď��g��ł䂭�K�v������B
�A
���ꂩ��͈�l�ЂƂ肪�����ōl���čs�����Ď��Ȏ������͂���ׂ��ŁA���𐭕{��Љ�̂����ɂ��ׂ��ł͂Ȃ��B�������A���̎��ɁA�l�͑��l�ł���A���̊e�l����������ɂ͘A�g����K�v������A�Ǘ����Ȃ��Љ�K�v�ł����B
�B
���̂悤�Ȕw�i�ŁA���F��̈ʒu�Â����������ƁA�d�@�n�̋Z�p�ҁA�����ҁA����҂͗l�X�ȕ���Ŋ��Ă���A�N��I�ɂ��L�����Ă���A��ω��l�̂�����̂ł���B���̒��ŁA�ӌ�������舒B�����邱�Ƃ͑�ϗL�p�ł���B���F��͊y�����𗬂������A������������A���ꂩ��V�����̐��ŗ��F����݂Ȃ���ƂƂ��ɂ���Ă䂫�����B
�Ƃ̂��b������܂����B
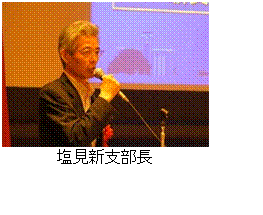 ���ɁA�I�ꑍ���������畽���Q�R�N�x�s���E�����v��m��l���c�ān�ɂ��Đ������s���܂����B�T���Q�X���ɊJ�Â��ꂽ������ɂ����āA��Ɉ��O�x������育��Ă̂������A��芈�����̈�Ƃ��āA�����Ƃ��Ď��������lj�����|�̎x�����ύX�̒�Ă����菳�F����A���c�O������������������ɏA�C�����|�̐���������܂����B�����ʼn����A������łȂ��Î�H�̊������ɂ��Ă��������ׂ��ł͂Ƃ����ӌ������������A�����V�x�������A�g��N���X����̉�����p���Ă��������Ƃ̉�����܂����B����ɉ����A���ƌÎ�Ƃ̌𗬓��ɂ��āA����̎x���s���^�c�ɎQ�l�ɂȂ�M�d�Ȃ��ӌ������������A��l���c�Ă͔���������ď��F����܂����B
���ɁA�I�ꑍ���������畽���Q�R�N�x�s���E�����v��m��l���c�ān�ɂ��Đ������s���܂����B�T���Q�X���ɊJ�Â��ꂽ������ɂ����āA��Ɉ��O�x������育��Ă̂������A��芈�����̈�Ƃ��āA�����Ƃ��Ď��������lj�����|�̎x�����ύX�̒�Ă����菳�F����A���c�O������������������ɏA�C�����|�̐���������܂����B�����ʼn����A������łȂ��Î�H�̊������ɂ��Ă��������ׂ��ł͂Ƃ����ӌ������������A�����V�x�������A�g��N���X����̉�����p���Ă��������Ƃ̉�����܂����B����ɉ����A���ƌÎ�Ƃ̌𗬓��ɂ��āA����̎x���s���^�c�ɎQ�l�ɂȂ�M�d�Ȃ��ӌ������������A��l���c�Ă͔���������ď��F����܂����B
���ɕ����Q�R�N�x�\�Z�v��m��܍��c�ān����������A����������ď��F����܂����B�Ō�ɁA�����Q�R�N�x�ɕĎ��E������}����ꂽ���X�i�Ď��U���A����Q�R���j�ւ̏j�����q�ׂ���ƂƂ��ɁA����蔏��������ďj�ӂ�\���܂����B
�@�ȏ�������āA�����Q�Q�N�x���F����x������͕�ƂȂ�܂����B
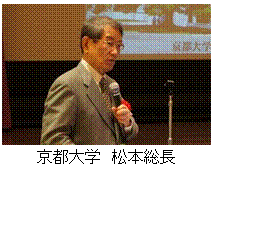 �@���������A�{����������ōs��ꂽ��A�P�U�����u����J�Â���܂����B���s��w���{�h���������}�����A�u��ЊQ���_�@�ɍl�����w�ƎЉ�̕������\���s��w�̌��݂̎��g�ݏЉ��Y���ā|�v�Ƒ肵�Ă��u�������������܂����B���{��������A�����{��k�Ђ��_�@�ɁA�������Ȋw�����^�C�����[�ɔ��M���邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ��F�����ꂽ�B��w�͍ō��w�{�̎g���Ƃ��āA����w�Ɠ��l�A����ɂ��Ă��l�X�Ȏ��g�݂��Ȃ���Ă���B�����ŁA�l�ނ̕������Ƃ��āu�����v�łȂ��u�ŖS�v�Ɍ������Ă���i�����̌͊��A�����A������@�j�̂ł͂Ȃ����B���̂悤�Ȑl�ނ̖��ɑ��Č��݂̊w��ł͉������Ȃ��A���l���A�ו��������x�ɐi��ł��錻�݁A�}�t�łȂ����ՓI����Ŗ{����Nj����閱�{�V�w���K�v�B�܂��A��w���Ȋw�I�m�������p�ł��Ă��Ȃ��A�O��������������K�v������ꍇ�ɁA�ԐړI�b���ɂ��A�٘_����������镵�͋C��Ŕj���ׂ��B���̂��߂ɂ͒���I�ɑO����q�ϓI�ړx���猩�������ł��鐧�x���K�v�A���̂��߂ɂ͑�w�͐ϋɓI�ɎЉ�Ƃ̌𗬂�}��ׂ��B�Ƃ����A��ϋ����[�����b�����������܂����B���ɁA���s��w�̌��݂̊����Ƃ��āA�ߔN�̐ݔ������A��܁A����g�s�b�N�A�L�����p�X�A�������_�̍ŐV�A��^�v���W�F�N�g�ɂ��Ă��Љ�������܂����B�Ō�ɁA�@�l����O���[�o�����ɂ�鋣�������̏ɑ��A���s��w�ł̎��g�݂Ƃ��āA�����v���W�F�N�g�ɂ��挩�I�Ȍ����҂̈琬�A���{�V�w�̒Nj��̂��߂́u�v�C�فv�\�z�A�Љ�Ƃ̌q���苭���̂��߂̐��X�̎{�����ɂ��ďq�ׂ��A��������擪�ɗ����āA���s��w�𖣗͓I�����C�ɂ��ӂꂽ���͂̂���ō��w�{�ɂ��Ă��������A�Ƃ����v�����`���܂����B
�@���������A�{����������ōs��ꂽ��A�P�U�����u����J�Â���܂����B���s��w���{�h���������}�����A�u��ЊQ���_�@�ɍl�����w�ƎЉ�̕������\���s��w�̌��݂̎��g�ݏЉ��Y���ā|�v�Ƒ肵�Ă��u�������������܂����B���{��������A�����{��k�Ђ��_�@�ɁA�������Ȋw�����^�C�����[�ɔ��M���邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ��F�����ꂽ�B��w�͍ō��w�{�̎g���Ƃ��āA����w�Ɠ��l�A����ɂ��Ă��l�X�Ȏ��g�݂��Ȃ���Ă���B�����ŁA�l�ނ̕������Ƃ��āu�����v�łȂ��u�ŖS�v�Ɍ������Ă���i�����̌͊��A�����A������@�j�̂ł͂Ȃ����B���̂悤�Ȑl�ނ̖��ɑ��Č��݂̊w��ł͉������Ȃ��A���l���A�ו��������x�ɐi��ł��錻�݁A�}�t�łȂ����ՓI����Ŗ{����Nj����閱�{�V�w���K�v�B�܂��A��w���Ȋw�I�m�������p�ł��Ă��Ȃ��A�O��������������K�v������ꍇ�ɁA�ԐړI�b���ɂ��A�٘_����������镵�͋C��Ŕj���ׂ��B���̂��߂ɂ͒���I�ɑO����q�ϓI�ړx���猩�������ł��鐧�x���K�v�A���̂��߂ɂ͑�w�͐ϋɓI�ɎЉ�Ƃ̌𗬂�}��ׂ��B�Ƃ����A��ϋ����[�����b�����������܂����B���ɁA���s��w�̌��݂̊����Ƃ��āA�ߔN�̐ݔ������A��܁A����g�s�b�N�A�L�����p�X�A�������_�̍ŐV�A��^�v���W�F�N�g�ɂ��Ă��Љ�������܂����B�Ō�ɁA�@�l����O���[�o�����ɂ�鋣�������̏ɑ��A���s��w�ł̎��g�݂Ƃ��āA�����v���W�F�N�g�ɂ��挩�I�Ȍ����҂̈琬�A���{�V�w�̒Nj��̂��߂́u�v�C�فv�\�z�A�Љ�Ƃ̌q���苭���̂��߂̐��X�̎{�����ɂ��ďq�ׂ��A��������擪�ɗ����āA���s��w�𖣗͓I�����C�ɂ��ӂꂽ���͂̂���ō��w�{�ɂ��Ă��������A�Ƃ����v�����`���܂����B
 �@�ߌ�T���S�T�����P��̍��e��Ɉڂ�܂����B
�@�ߌ�T���S�T�����P��̍��e��Ɉڂ�܂����B
�@�����V�x�����̊��t�̂������Ŏn�܂������e��́A�r�Q�R������g�P�X���܂ŁA���L���N��w�ɂ킽�鑽�ʂȎQ���҂̌𗬂̏�ƂȂ�܂����B�������͂�ʼn���̕��X�̊����Ȉӌ��������s���钆�A���d�������A����p�\�R���A�X�s�[�J�[���������܂�Ẵ{�[�J���C�h�i�̐������\�t�g�j�̉��t������I���������A��Ϙa�₩�ȕ��͋C�ƂȂ�܂����B���̌�A����V��v�����̉����ɂ��A�P��́u���i�Ύ��q�̉́v���������A�Ō�ɏ��V�V���x�����̒����߂ɂ��ߌ�U���R�O���ɎU��ƂȂ�܂����B

���i�Ύ��q�̉̍���
[��]�@���F��@�����x���@���������@�I�꒼�l�i�g�O�S�N�d�q���j
�Q�D�H�̍u�����E���e��
����23�N11��29���i�j�@18:30�`20:30
�ꏊ
�w�m��ف@210����
[�Z��]�@�@��101-8459�����s���c��_�c�ђ�3-28
[�d�b]�@�@03(3292)5936
[�A�N�Z�X]�@�n���S�s�c�O�c�� �s�c�V�h�� �������g���������
�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ے��w�iA9�o���j�k��30�b
[URL]�@
http://www.gakushikaikan.co.jp/info/access.html
�u����
�Ɨ��s���@�l�@�����w������
������X�[�p�[�R���s���[�^�J�����{�{��
�v���W�F�N�g���[�_�[�����{����
�n�� �� �i�킽�Ȃ� �������j�@�l
�X�P�W���[��
18:30�`19:30�@�u����
19:30�`20:30�@���e��
���
�u����͖����B���������A�����e����J�Ái���F2,000�~�j�B
��
����23�N11��29���Ɋw�m��قɂĊJ�Â���܂����A���F����x���H�̍u����ł́A�P�O�y�^�t���b�v�X�X�[�p�[�R���s���[�^�u���v�Ƒ肵�܂��āA�����w������������X�[�p�[�R���s���[�^�J�����{�{���̓n�Ӓ�l�ɂ��u�����Ղ������܂����B�}�X�R�~�ł��L���ƂȂ������E�ň�ԁi��Ԃł͂Ȃ��j�̋Z�p�ɉ�����̊S�������A70������Q���҂��}���āA��ύ��x�ȓ��e�ł���Ȃ���ƂĂ�����₷����������������A��Ϗ[�������u����������Ƃ��ł��܂����B
�n�ӗl�͓�����w�d�C�H�w���������ƌ�A���k��w�Ŕ��m�ے����C������A���{�d�C�ɂăR���s���[�^�[�A���C���t���[���A�X�[�p�[�R���s���[�^�Ƃ������A�d�q�������{�̍������Ƃ�S���Ă����āA2006�N��荑�ƃv���W�F�N�g�̌����U���ǁA���̌㗝���w�������ɂăX�[�p�[�R���s���[�^�[�̃v���W�F�N�g�}�l�[�W�����g�Ɍg����Ă���ꂽ�o�����������ɂȂ��Ă���܂��B
�u�X�[�p�[�R���s���[�^�̒�`�Ƃ́v�A�u�X�[�p�[�R���s���[�^�ʼn����ł��邩�v�A�Ƃ�������{�I�ȉ������n�܂�A�C��ϓ��\����Ôg�̉�́A�V��J���Ȃǎ������̐����ɔ@���ɍv�����Ă��邩����̗�������Ă��Љ�������܂����B�b��́u���v�ɂ��Ă̊J���w�i��A�u���E��v�����������Z�p�̂��Љ�A���E�̃��C�o�������Ƃ̊W�Ȃǂɂ��āA�����҂Ȃ�ł͂̂ƂĂ����C�u�����邨�b�Ղ��邱�Ƃ��ł��܂����B���ɓ��{�炵�����݂Ƃ��ĐM������ȃG�l���͒f�g�c�Ƃ̂��ƁA�X�R���̍������V�X�e���⍂����Ԃł�29���ԈȘA���ғ��Ȃǂ́A���C�o�������|���鐫�\�Ƃ̂��ƂŁA�ƂĂ��ւ炵�����b�����������܂����B
�Z�p�I�ȗv�_�ɂ��Ă����������������A10�y�^�̉��Z���\�A45�i�m�ėp�X�J���v���Z�b�T������V�X�e���A8���ȏ�̃v���Z�b�T���Ȃ���l�b�g���[�N�Z�p�A����œK���R���p�C���Z�p�A���M�����Z�p�A�Ƃ������Ő�[�Z�p�ɂ��Ă�������₷����������������܂����B�Ő�[�Z�p�݂̂Ȃ炸�A�u�g����Z�p���v�Ƃ����v�z�̂��ƂɁA���܂��܂ȉ^�p��e�Ղɂ��邽�߂̍H�v�A�W���u�X�P�W���[���A�f�t�h�x�[�X�̃C���^�[�t�F�[�X�A�W���I�ȃv���O�������Ȃǂɂ��Ă����������������āA�l�X�Ȍ����J���̌���Ŋ��p����Ă��邱�Ƃ��m�邱�Ƃ��ł��܂����B�܂��A�u���R���s���[�^�O�v�Ɖw�����t���قǂɋ���Ȏ{�݁A50���[�g����60���[���̖����̃R���s���[�^���[����A�J�����p���̍ė��p�A���z���p�l���A����Ή��Ƃ��������ւ̎��g�݂Ȃǂɂ��Ă��A���Љ�������܂����B
�Ō�ɁA�ϋɓI�ɐ��̒��ɖ𗧂��Ă��邱�Ƃ��O�����M���A���Ǝd�������̋t���ɕ������ɓ��{�̉Ȋw�Z�p��U�����Ă䂭���Ƃ̏d�v�����q�ׂ��āA�u������̂����ɏI���邱�Ƃ��ł��܂����B

[��]�@���F��@�����x���@��v�����@����m���i�g�O�T�N���j
�R�D���w��E���s��
�t�̗��s��i����24�N3��3����JAXA���z�q��F���Z���^�[�j
��N�͐k�Ђ̉e���ɂ�蒆�~�ƂȂ��Ă��܂��܂������s��ł����A���̓x�͐��V�Ɍb�܂�60�]���̎Q���҂��}���āA�����̂����ɉF���q���J���@�\�iJAXA�j���z�q��F���Z���^�[���w����s�����Ƃ��ł��܂����B���f���T���@�u�͂�Ԃ��v�̑劈��̉e��������Q���҂̊S�������AJAXA�l�̓��O�ȏ����̂���������܂��āA��Ϗ[���������e�̌��w��������Ƃ��ł��܂����B
���߂ɉF���q���J���@�\�����A�ΐ엲�i�l�̂����A�Ղ�����A3�ǂɕ�����āA�W�����A�����{�݁A�������̌��w�����Ԃɍs���A�f����ڂ������������Ă��������܂����B�W�����ł́A�ŐV�W�F�b�g���q�@�ɂ��Z�p���Ă���Y�f�f�ދZ�p�A���^�����������@�A���Y���̃^�[�{�t�@���G���W���ȂǁA���{�̍q��F���Z�p�̃}�C���X�g�[�����Ȃ��e��Z�p�̏ڂ�������Ղ��������܂����B�����{���w�ł́A����ȋɒ����������ݔ��̓�����A�����Ȏ����p���f����q�������Ă��������A�@�̐v�̃v���Z�X����A����܂œ��{�̍q��Z�p���x���Ă��������ő�K�͂̕��������̑��Ղɂ��Ă���������������܂����B�������ł́A�������T�������t�B�[���h�Ŏ����p�̒T���@���f���̃f���������Ă��������A�����J���ɂ܂��l�X�ȃ`�������W�⏫���̃r�W�����ȂǁA�m�I�D��S�ɖ��������b�Ղ��邱�Ƃ��ł��܂����B
������Ή��ɑ���Ȃ��s�͂�����������JAXA�������i���̏��i�`�a�l����́A�u�������i�I�Ȍ����J����ʂ��āA���{�̍q��F������̔��W��ڎw���Ă䂭�̂ŁA���w���ʂ��đ����̕���JAXA�̃T�|�[�^�[�ƂȂ��Ă���������Ɗ������ł��v�Ƃ̒g�������b�Z�[�W�����Ղ������܂����B
���w�̌�͋ߗׂ̘V�܋������ɂāA���V���x��������̈��A�̌�A������Ȃ��ċA�H�ւ��܂����B�Ȃ������͋ߗׂ̐[�厛�ɂāu����s�v������Ɍ_��s���Ă���A���H��ɂ���s�Ɍ������ďI���y���܂ꂽ���X����������Ⴂ�܂����B
���w��𐬌����ɍs�����Ƃ��ł��A���߂�JAXA�l�n�ߏo�Ȏ҂̊F�l�A�W�ҏ����̂����͂Ɋ��ӂ�\���グ�����Ǝv���܂��B

�m�n�@���F��@�����x���@��v�����@����m���i�g�O�T���j
�S�D��̉�
|
�@ |
���� |
�@ |
|
(1)�͌�� |
�쑽�� �� �i�r�R�U���j�A���� ���T�i�r�S�P���j |
�͌��s���ē� |
|
(2)������ |
���c �ǒm �i�r�R�W���j |
������s���ē� |
|
(3)�S���t�� |
���V�@�v��i�r�R�T��)�A�R�V�@���i�r�R�W���j�A��@�m�i�r�S�O���j |
�S���t��s���ē� |
|
(4)���w�� |
����@�O �i�r�R�U���j |
���w��s���ē� |
|
(5)�e�j�X�� |
�R���@�p���iS44���j�A�c���@��j�iS44���j �A�����@�m�iS46���j |
�e�j�X��s���ē� |
�T�D�g��N���X��
|
���� |
����23�N�x�@���� |
�@ |
|
|
(�P)���ڂ��m�r�Q�P�`�r�Q�S���n |
�M�c�@���j�iS�Q�S���j�A��e�@�_�j �i�r�Q�S���j |
���ڂ��s���ē� |
|
|
(�Q)�܋㗌��m�r�Q�T�`�r�Q�X���n |
�c���@�W�i�r�Q�X���j |
�܋㗌��s���ē� |
|
|
(�R)�݂Ƃ�����m�r�R�O�`�r�R�S���n |
���R�@�\��Y�i�r�R�P���j�A�⌴�@ᩈ�i�r�R�P���j |
�݂Ƃ�����s���ē� |
|
|
(�S)���ɉ�m�r�R�T�`�r�R�X���n |
���]�@����i�r�R�V���j |
���ɉ�s���ē� |
|
|
(�T)������m�r�S�O�`�r�S�S���n |
�u��@���i�r�S�R���j |
������s���ē� |
|
|
(�U)���k��m�r�S�T�`�r�S�X���n |
����@���M�i�r�S�T���j�A���d�@�N�v�i�r�S�U���j |
���k��s���ē� |
|
�U�D������
�����F�@����23�N5��29���i���j�@12:00�`15:00
�ꏊ�F�@�w�m��ٖ{�فi2�K203��c���j
�@�@�@�@�@�@�Z���F��101-8459�@�����s���c��_�c�ђ�3�|28
�@�@�@�@�@�@�d�b�F03�i3292�j5936
�@�@�@�@�@�@��ʁF�n���S�s�c�O�c���܂��͓s�c�V�h���܂��͉c�c�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�ے��w�i�`9�o���j�k��30�b
�@�@�@�@�@�@http://www.gakushikaikan.co.jp/info/access.html
�o�Ȏ��F�@�����A�]�c���A�����@�v28��
�@�@�@�@�@�@�����o�ȎҁF�@��� �x�����iS44 ���j�A���� ���x�����iS45 ���j�A���V �Ď��i�r46���j�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c ���������iH03 ���j�A�I�� ��v�����iH04 ���j�A ���c ���������iH04 ���j
����F�@����
��ȋc���F
�`���̈��x�����̈��A�̍ہA�����{��k�ЂŖS���Ȃ�ꂽ���ւ̖ٓ����s���܂����B
(1) �����Q�Q�N�x�s���E������
���F
�u�����̘A�����m���@�ɂ��āv
�@�{��
�y���[�����̐����z
rakuyukai.org�h���C�����e��ē��̃��[���𑗕t����悤�ɂ����B���܂Ń��[�����̒��B������Ɉˑ����Ă������A��ƃZ�L�����e�B����������钆�A�x���Ƃ��Ăǂ��Ή����邩���ۑ�ł������B���ݗ��p���Ă��郌���^���T�[�o�[�̘g�g�݂̒��ŗ��p�ł���悤�ɂȂ������߁A�����x���̎x�o���V���ȕ��S�͔������Ă��Ȃ��B�����A�ꕔrakuyukai.org�h���C�������₳��郁�[���A�h���X������A�X�ɑΉ����Ă���ł���B������������`�F�b�N���A�������ɕ��S�̊|����Ȃ��`�ł̘A����i�̊m�ۂ��s�������B
�܂��A�g�у��[���ő��M���Ăق����Ƃ����v�]���ꕔ�ł��邪�A�g�у��[���̋@�\��������ւ̕��ׂ��傫�����ߓ���B����Arakuyukai.org�Ƃ����h���C�����瑗��Ƃ������[���Ǝ��m���邱�ƂƂ��A�ʂɎ�M�ݒ蒸���l�A���肢���Ă䂭�B
�y����A�����i�C�z
���s��w�ł́A���Ɛ��̃l�b�g���[�N�m�ۂ̂��߂̎�i�Ƃ��āA�u����A�����i�C�v���J�݂��Ă���@�� http://www.alumni.kyoto-u.ac.jp/�@�B�@����Ǘ��̖ʂŁA��������������ōX�V�ł��铙�A����̉���Ԃ̘A���A�����ɗL�����p�ł���\��������B�l���Ǘ��̖ʂŎx���̃f�[�^���ڍs���邱�Ƃ͏o���Ȃ����A����A�x���Ƃ��Ċ��p�𑣂��čs�������B
�A�ӌ��E�v�]
�E���݁A�x���ł̖���͂ǂ��Ǘ����Ă���̂��HS30���A�w�N�ɂ���Ă͖��됮��������Ă���w�N������B�w�N���ƂɊǗ���������ǂ��̂ł͂Ȃ����B
�E�w�N�������A����s���Ƃ͂ǂ��������Ƃ��H�s���ł͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����H
�B�x���Ƃ��Ă̑Ή�
�E���������`��v��������N���Ƃɑ�ւ�肵�G�N�Z���ɂĊǗ����Ă���B�v�����̓o�^�T�C�g�̏����A���e����œo�^���Ă���B��l����x������̖���̊Ǘ��͊����̑傫�ȕ��S�ƂȂ��Ă���B�{���ł�����Ǘ����Ă���̂ŁA�{������Ƃ̐����A�{������̗��p�����������Ă䂫�����B
�E�w�N�����̊Ǘ����Ă��閼��ŁA�x���ɏo������̂͏o���Ă��炢����������Ă䂫�����B�������A�w�N���ƂɊ����̃��x���ɍ�������̂ŁA�w�N�����ɂ��ׂĂ��˗����邱�Ƃ͓���B
�E���[����t��������s���ƂȂ����w�N������A����s���Ƃ��ĕ\�L���Ă���B�����A�ԐM���Ă��Ȃ��w�N�����������A�{���ɘA�����͂��Ă��邩�A�{�l���w�N�����ƔF�����Ă��邩�͔c���ł��Ă��Ȃ��B�����A���̕��ֈ˗������s���K�v���͔F�����Ă��邪�A�܂��Ή��ł��Ă��Ȃ��B���㌟���������B
(2) �����Q�Q�N�x���Z����ъč���
���F
(3) �����Q�R�N�x�̖����^�]�c���^����
���F
(4) �����Q�R�N�x�s���E�����v��
���F
�u������A����̓����Ɋւ��āv
������A����͂���܂œ��j���ɊJ�Â���Ă������A�y�j���J�Â�]�ސ�������B��N�x�̊�����ŁA�����Ɉ�C����邱�ƂƂȂ����J�×j���ɂ��āA������Ɋւ��Ă͏����̓s������������������j���J�ÂƂ������B����͉��\��̓s�������邪�A�{�N�x�͓y�j���J�ÂƂ���B
�u������� �����������̌��v
���܂Ŏ�����͍����l�iS62�d�U���j�̂��D�ӂŊ������������������A���܂łS��J�Â���Ă����B��芈�����͎x���Ƃ��Ď�v�ȉۑ�ł���A�������������p�����Ă䂭���Ƃ��]�܂������A�����l�ɕ��S������������ׂ��ł͂Ȃ��BH23�N�x���A�J�×v�|�A�菇�𗝉����Ă��鑍���������C���I����ɒS�����邱�Ƃ�O��Ɂu��������v�𐳎��Ȗ�E�Ƃ��A���L�A�݂͂̉��������x�����U���ɒlj����A���肷�邱�Ƃ�������������Ă��ꂽ�B
����ɂƂ��Ȃ������Ƃ��Ă̔C�������т錜�O�����邪�A��芲������́A�u���F����ɂ��Ѝv���������Ƃ����C���������A����I�Ɏd���̓s����D�悹����Ȃ��Ƃ������X�N������Ƃ������Ƃ�F���������������B������ɂ������Ă̌��O�����́A��C�����߂Ȃ��Ƃ��邸�鉽�N�����Ȃ�������Ȃ��Ƃ������͋C�ɂȂ邱�Ƃƍl���Ă���B�C���̋K���͌��߂��ق����悢�Ǝv���B�v�x��������́A�u�`���I�ɂ͎���I�ɑΉ����Ă����Ƃ������Ƃł���̂ŁA����Ɋ��҂������v�ƃR�����g���������B
�܂��A�����đ���ɂč����l�֘J���˂��炤������s������̈ӂ�\���邱�ƂƂ����B
�x����ύX��
|
��U���@�{�x���ɂ͎��̖�����u���B �i�V�j������� ���������������B
�R�D �C�� �S�D ������ �����͖������g�D���A����̕t�c�������܂߁A�{�x���̖ړI�B���̂��ߏd�v������R�c��������ɒ�Ă���B |
(5) �����Q�R�N�x�\�Z�v��
���F
�iH22�N�x�����{���Ă���u���N�x�J�z���̓K�����v��2�N�ڂł���A���������x�o�z���Ă���B�j
(6) �Ď��E����̂��j��
���F
�V�D��芲����A�������A���𗬉�
�����Q�S�N�Q���Q�P���i�j�P�X�����i��C���^�[�V�e�BA���Q�V�K�̋��s��w�����I�t�B�X�ɂāA��T���������J�Â����B����͓����H�Ƒ�w��w�@��H�w�����Ȃ̔��ؓ��y���������}�����A�u�q�g�Ƌ@�B��]�E�_�o�̃��x���łȂ��_�o�C���^�t�F�[�X�v�Ƒ肵�āA���u���������B
�@���O�̎Q���\�����݂R�R���ɑ��Q�U���i���a���P�S���A�������P�Q���j�̎Q��������A���e��ɂ��Q�O���ȏ�̕����Q�����ꂽ�B
�@���u���́A�u���C��-�}�V���E�C���^�t�F�[�X(BMI)�A �u���C��-�R���s���[�^�E�C���^�t�F�[�X(BCI)�A�_�o���(NeuralProstheses) �Ȃǂ̐_�o�C���^�t�F�[�X (NeuralInterface)�ł���A�q�g�Ƌ@�B��]�E�_�o�̃��x���łȂ��Z�p�Ɋւ��āA��\�I�Ȑ_�o�C���^�t�F�[�X�̌���܂ő̌n�������Љ�����B
�@��b�ƂȂ��w�E�����w�̒m����H�w�Z�p�̘b��D������Ȃ���̔��ɖ��x�̔Z�����e�ŗ\����Ă̂P���ԂP�T���قǂ̂��u���ł͂�������NHK�X�y�V�����̉f����A�f�����������Ă��������A���u�҂͔��Ɏ䂫���܂�Ă����B
�@�f����EOG�X�C�b�`��p���Ėڂ����ɓ����������ɂ����u�U�[���Ȃ�Ƃ������̂ł��������A�ؓd����p���Ă���̂ł͂Ȃ��A�p���i�v���X�j�ƖԖ��i�}�C�i�X�j�Ō`�������_�C�|�[���ɂ����̂ŁA��10mV�̓d�ʍ������o���Ă���Ƃ��������ɂ͉�����������̐����R�ꂽ�B
�@�Ō�Ɍ��ݐi�s���̌����ł��鍂���ׂȐl�H���o���������邽�ߍĐ���w��MEMS�Z�p��Z�������u�o�C�I�n�C�u���b�h�^�l�H��v�̂��Љ�ɉ����A�����I�ɂ͋@�\��ւ���@�\�U���ɐi��ł䂫�����Ƃ����z��������A�u�����I�������B
�@�d�C�n�o�g�̉�X�ɂƂ��Ă��܂����݂̖�����������Ɗ������Q���҂����Ȃ��͂Ȃ������悤�����A�����̐g�̂��d�C�M���ł��邱�Ƃ����߂ĔF������������̂ł���A���͂⒮�͂��Ȋw�̗͂ŕ���Ă����p���A���p������Ă���Z�p�A�����ւ̓W�]�Ȃǂ��_�Ԍ��A�Q���҂��ꂼ�ꂪ������������̂������A�邱�Ƃ��ł����u����ł������悤�Ɏv���B

�u�����i�F���؏y����

EOG�X�C�b�`�̃f���i�g�O�W���̓��C�l�A���؏y�����j
�m�n�@���F��@�����x���@��������@�@���c�ƌȁi�g�O�R���j
�ȏ�