H26�N�x ��̉�&�O���[�v����
H25�N�x�̕��͂�����
�e�����̕��ցF�f����]�������������������܂�����A��̖��̂ƌf�����e�����������փ��[�����ĉ������B
��̉�
|
�@ |
���� |
|
�쑽�� �� �i�r�R�U���j�A���� ���T�i�r�S�P���j |
|
|
�t�R�@���O �i�r�R�X�C���j |
|
|
���V �v��i�r�R�T��)�A�R�V ���i�r�R�W���j�A��� �m�i�r�S�O���j |
|
|
���� �O �i�r�R�U���j |
|
|
�R�� �p���iS44���j�A�c�� ��j�iS44���j �A���� �m�iS46���j |
�g��N���X��
|
�@ |
���� |
|
�M�c ���j�iS�Q�S���j�A��e �_�Y �i�r�Q�S���j |
|
|
���� �O�@�i�r�Q�V���j |
|
|
��c�@����@�i�r�R�S���j�A���U�@�h�F�@�i�r�R�S���j |
|
|
����@�O�@�i�r�R�U���j�A�O��@���v�@�i�r�R�U���j |
|
|
�X�c�@�_�O�@�i�r�S�P���j |
|
|
���R�@��i�r�S�V���j�A�@�r�@�a�v�i�r�S�W���j |
|
|
�ɓ��@����@�i�r�T�S���j |
���͌��@�@�����F�쑽�� �� �i�r�R�U���j�A���� ���T�i�r�S�P���j
����26�N�x�͌�����
H25�N�x���ɍ���ɂ��J�Ò��~���������̂�H26�N�x��4������H27�N3���܂Ńt����]��4��J�Â��A�Q���l���͂��ꂼ��15�l�A19�l�A19�l�A22�l�ł������B�ߋ�10�N�Ԃł̍Œ�L�^��16�l��20�l������邱�Ƃ͖w�ǂȂ��������AH26�N�x�͕��ς�20�l���������тƂȂ����B�Q���l���̋}���ɓ��ʂ̗��R�͌������炸��X�̌��ۂƎv���邪�A���̐V�K�Q�������ł��ɂȂ��Ă���̂ŏ�������������X���ɂȂ�̂͂�ނȂ��B
��������F
H25�N�x�͊��c���Y�� (S37��)�A�g�c������(S40��)�̂Q���̐V�K�������������B���݁A�o�^���������60���ŁA��N�x���3�����ł��邪�A�މ�̐\���o�̂��������X�͉ߋ��w�ǎQ������ĂȂ����X�Ȃ̂Ŏ����I�Ȍ����ɂ͂Ȃ��ĂȂ��B
��������̂����Q�����т̂���l 51���A��x���Q�����ĂȂ��l 9���ƂȂ��Ă���B
���N�ʉ������S20�N�� 11���AS30�N�� 27���AS40�N�� 21���AH�N�� 1���ƂȂ��Ă���A���N�ʍ\����͂������N�Ԃő傫���ς���Ă͂��Ȃ��B
���N�̌J��Ԃ��ɂȂ邪�AS40�N��㔼�ȍ~���̎Q�����ؖ]�����B
�^�c�����F
�Ǖ����͊e���̎��_�ɂ��n���f�B�L���b�v���Ƃ��A�ߌ�̔����̎��ԓ��i���� 1���`6���j�Ɋe���R��
�ǂ�W���Ƃ��āA�ŏ��̂R�ǂ̐��тɉ����ďܕi�i�}���J�[�h�j��i�悵�Ă���B���Ԃ̋�����l�͂S�ǖڈȍ~�̑ǂ����R�ŁA���ʂ͎���̎��_�ɔ��f����������Ƃ��Ă���B
E-mail�̕��y�ɂ��A�}�ȃL�����Z����}�ȎQ���ւ̑Ή��������悭�������ł���悤�ɂȂ�A�Q���l���ƑǏ����Ȃ���A�����������̒�����ܕi�̓�������ߍׂ����ł��邾�������̎Q���҂ɍs���킽��悤�ɂ��ĎQ���҂̃��`�x�[�V�������グ�Ă���B
�Q���Ґ��Ɛ��сF
�e��̎Q���Ґ��A���їD�G�ҁi3��S���ҁj�͈ȉ��̒ʂ�i���N���A�h�̗��j
�� ��1��iH26�N4��27���j
�Q���� 15��
�@�@�D�G�ҁ@ �i�Ȃ��j
�� ��2��iH26�N8��31 ���j
�Q���� 19��
�D�G�� ���C�ꐬ�iH 8���j
�� ��3��iH26�N12��14���j
�Q���� 19��
�D�G�� ���C�ꐬ�iH 8���j
�� ��4��iH27�N3��15���j
�Q���� 22��
�D�G�� ���J�ǏG�i35���j
3��S���҂͖���2�`3���͏o�Ă��邪�AH26�N�x�͑�P��[���A��2��ȍ~���e1�������o�Ȃ������̂�
�i�N�̃f�[�^�~�ςŃn���f�B�L���b�v���K�������ꏟ�s���������Ă��錻���Ƃ�������B
�͌��́u�C�y�ɎQ�����A�C�y�Ɋy���ށv���Ƃ����b�g�[�ɁA���J�Ó����O�ł̎Q���������ɂ��t���L�V
�u���ɑΉ����A�W���E���U�̎��Ԃ��X�l���R�ɂł���A������u�D���Ȏ��ɗ��čD���Ȏ��ɋA��v������
�Ƃ��Ă���B�܂��A�����_���̃n���f�B�L���b�v�̗p�ŁA�ǂ�ȂɊ��͂̍��������Ă��Γ��ɑǂł��A
�ՑO�ɑ�����ΐe�q���قǂ̔N��ɊW�Ȃ��A�N����z���Ęa�₩�ȕ��͋C�őǂ��y���ނ��Ƃ�
�ł���̂ŋ����̂�����͂ǂ����C�y�ɂ��Q���������������B
�ȏ�
��������@�@�����F�t�R�@���O �i�r�R�X�C���j
����26�N�x���������
����P�O�P��@�����Q�U�N�X���Q�V���i�y�j �����u�V�a�v
�Q���҂W��
�Q�[���̓W�J�́A��P���ڑ�Q���P�ʁi�Q�W���_�j���i�̒��c���iS�R�W���j�����̑�Q���ł���P�ʁi�Q�P���_�j��A��A���̂܂ܓ������Č����D�������B���c���̗D���́A�ʎZ�S��ڂŗ��Q�ʃ^�C�̋L�^�ƂȂ����B���D���́A��P���ڑ�P���P�ʁi�R�Q���_�j���i�ł��̌�������ɐi�߂��n粎��ƂȂ����B�Q�[���̑S�̓I�ȓW�J�Ƃ��ẮA��Q����Q�쓌��e�Ԃ̐����iS�R�W���j���u���[�`�A�ꔭ�c���i���j�A�O�Í��A�_�u���A�h���i���j�R�c�P�Q�|�c�e�Q�{���v���ő�̂�����i�a��j�ŁA���҂��ꂽ�R�N�Ԃ�̖��Ȃ��A�I�~�قڌ����ȓW�J�ł������B
�@�Ȃ��A�o���G�e�B�܂̈�Ƃ��Ă�����݂́u�����܁v��ݒ肵���B����́A�J�Ó��̂Q�V���ɂ��Ȃ݁A���v�̂Q�܂��͂V���h���ɂȂ������A������g���Ă��������̍ł������v���[���[�ւ̏܂Ƃ����B����͂S�l�����̂������B���������A���v�Q���������l�B���������c������܂����B
[���ʏ�]�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ [�o���G�e�B��]
�D�@�� ���c�� �iS�R�W���j ��g�� �t�R�� �iS�R�X�C��
���D�� �n粎� �iS�Q�W�����j ���g�� ���V�� �iS�R�W���j�@
��R�� ���{�� �iS�R�R���j�j ���_�� ��� �iS�S�R���j
��S�� ���� �iS�R�W���j ������ ���]�� �iS�R�V���j
��T�� ��� �iS�S�R���j ������ ���c�� �iS�R�W���j
B B �� �t�R��
�iS�R�X�C���j
����P�O�Q��@�����Q�V�N�R���V���i�y�j �����u�V�a�v
�@�Q���҂W��
�O���͓�\�l�ߋG�̈�ł���u�[孁v�ɂӂ��킵���z�C�ł������B�������A�{��̊J�Ó��͐�������̓~�^�̋C���z�u�ŁA�J�オ��̔��������߁A�O�X�܁X�Q�W�����ʁX�́A�C�̂������g�̈������܂�X�^�[�g������B
�@���ُ̈�ȋC�ۂ̉e�������̂��A�Q�[���̐i�s�͑�r��ƂȂ����B���̒��ő�Q�A�R�A�S���Ńg�b�v��A�悳�ꂽ��㎁�i�r�S�O���j���A�{�W�R�̃u�b�`�M���́A�������A���D���ł������B���̃����o�[�͂��̗]�g������������ꂽ�B�Ⴆ�A�������e�̑�S��퓌�R�ǂŁA���[�`�E�P�p�c�E�c���E��C�ʊсE�h���P�Ƃ����e�n�l���̂U�O�O�O�I�[���Ƃ��������U��ł������B�Ȃ��A���`�����S�S��̍��v���{�W�R�Ƃ����L�^�́A�����ł̊J�Â̂��ߎ��Ԑ�����݂�����W�W��ȍ~�̍ō��_�ƃ^�C�L�^�ł���B
�@�܂��A���D���͜A�쎁�i�r�S�R���j�ŁA�R���I�����̑�T�ʂ���̑���i�ł������B�Ȃ��A�����͎Q���S��ڂ̏��D���ŁA���̋L�^�́A�h�Q���Q�Ȃ����R��ڂŁA�D���܂��͏��D���������h�Ƃ����{������̃W���N�X�̈�ɏ�������̂ł������B
[���ʏ�]�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ [�o���G�e�B��]
�D�@�� ��㎁ �iS�S�O���j ��g�� �n糎� �iS�Q�W�����j
���D�� �A�쎁 �iS�S�R���j ���g�� �t�R�� �iS�R�X�C���j�@
��R�� �n粎� �iS�Q�W�����j ���_�� ���c�� �iS�R�W���j
��S�� ���c�� �iS�R�W���j ������ �]�㎁ �iS�S�P���j
��T�� �]�㎁ �iS�S�P���j ������ ��� �iS�S�R���j
B B �� ���c�� �iS�T�O���j
�ȏ�
���S���t��@�@�����F���V �v��iS�R�T���j�A�R�V ���iS�R�W���j�A��� �m�iS�S�O���j
����26�N�x�S���t�����
�����Q�U�N�x�͂P�O���P�T���ƂR���R�P���ɂQ��R���y���J�Â��Ă��܂��B�����Q�V�N�R���̊J�Â͍��̖��J�����҂��ĂQ�V�N�R���R�P���ɖ{���b�b�ŊJ�Â��܂������A�P�T�ԑO�ɊJ�Ԃ������͒��x���J�ƂȂ��Ă���A�C�����オ���Ă��̏�Ȃ����K�ȃS���t���y���ނ��Ƃ��o���܂����B�J�Ó��A�J�Ïꏊ�A���҂͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
² ��P�Q�W���@�����Q�U�N�P�O���P�T�����J�@�{����CC�@�Q���҂P�X���A �D���F�є����ꎁ�i�R�P���j�A���D���F�h�����F���i�Q�W���j�A�R�ʁF������M�ꎁ�i�R�U���j
² ��P�Q�X��@�����Q�V�N�R���R�P�������@�{���b�b�@�Q���҂Q�O���A�D���F�c��@�M���i�S�S���j�A���D���F����@�O���i�R�U���j�A�R�ʁF �����lj�i�Q�W���j
�@���F��S���t�͏t�H�N�Q��J�ÂƂ��Ă���A�t�͍��̖��J������_���ė\�Ă���ɂ��S��炸�A���̔N�̓V��ɂ��t���ł��������Q�݂ł������肪�Q�N�����Ă̂ł����A���N�͍K�^�ɂ����J�Ă邱�Ƃ��o���܂����B
�@�Ⴂ�l�̎Q�������Ȃ��Q���҂̍�����i��ł��܂����A��P�Q�X��͎���\�i�Ƃ��ĐV���������i��v�S���j�������Ă��ꂽ���a�S�S�N���̓c��@�M�����D������܂����B�܂��A�Q���Ғ��̍ō���҂ł��鏺�a�Q�W�N�������s��w���̕����lj���R�ʂɓ��܂���A�����Q�W�N���̓n粁@�`�Y�������b�L�[�Z�u���܂��l�������Ȃnj��C�ȂƂ���������Ă��������܂����B��P�Q�W��ɂ͓������a�Q�W�N���̘h�����F�������D������Ă���A�Q�W�N���̌����Ԃ肪�ڗ����܂��B
�@�����P�O�N�Ԃ̎Q���Ґ��̐��ڂׂĂ݂�ƁA�����P�W�N����Q�O�N�͕��ςQ�W���Q���A�����Q�T�N����Q�V�N�͕��ςQ�Q���Q���Ƒ傫���������Ă��܂��B����A���̌J�z�����P�O�N�O�ɂ͂V���~��ł��������A�ʐM��i��e���[���ւ̕ύX�ƃp�[�e�B�[�ł̐H���̐ߖ�ɂ���ĂR�O���~����قǂɑ��������̂ŁA��P�Q�X��Q������P�O�O�O�~�Ƃ��āA�o���邾�������̐l���Q���ł���悤�Ȋ��ɂ��Ă��܂��B
�@�S���t���D�҂̍���ŔN�X�Q���҂��������Ă��܂����A�W�T�ɂȂ�ꂽ�Q�W�N���̑��y�̂���������K���A�W�O���Ă����N�Ȑ����𑗂邽�߂ɂ��S���t�ɎQ�����ĕ����Ă݂܂��B����ɁA�X�R�A�J�[�h���������Ċe�z�[���ʼn��Ԃ̃N���u���g�p���A�{�[���̈ʒu���ǂ������������v���o���Ă݂�̂��{�P�h�~�̌P���ɂȂ�܂��B�S���t�̌��p�̈�ł��B
�ȏ�
�����w��@�@�����F���� �O�i�r�R�U���j
����26�N�x���w�����
�w���3��J�Â��܂����B
1�j��148�w��
�@�@�ȖځF�@����(��)�@�(��)�@�䓛(��)�@��@�t(��)
2�j��149�w��@����26�N12��23��(�j)
�@�@�ȖځF�@�J��(��)�@�o�� (��)�@�D�ٌc(��)�@��{(��)
3�j��150�w��
�@�@�ȖځF�@����(��)�@����(��)�@�O�R(��) �@�m��(��)
�@���Ɗϐ����Ŗ���2�Ȃ��w���Ă��܂��B�Ȃɂ���������낢��ł����A����ƂȂ����̂��ÂтȂ���吺���o���āA�y����ł���܂��B�w�̂��o���̂�����������܂����琥�Q�����������B�i���݉��12���j
�ȏ�
���e�j�X��@�@�����F�R���@�p���i�r�S�S���j�A�c�� ��j�i�r�S�S���j�A���� �m�i�r�S�U���j
����26�N�x�e�j�X�����
���F����x���e�j�X��́A���a60�N�ォ��قږ���1��̃y�[�X�ŏT���̗����𑱂��Ă��܂����B�ŋ߂ł́A�ȑO����ʏ�̗����s���Ă������c�J�̑呠���^����ɉ����āA�����q�ː��X�|�[�c�����̃R�[�g���m�ۂ��āA���ϓI�ɂ͖������ȏ�J�Âł���悤�ɂ��Ȃ�A�֓����̍X�ɍL���͈͂���̉���̊F�l�̎Q�������҂ł���悤�ɂȂ�܂����B
����26�N�x���тƂ��ẮA13��̊J�Â��v�悳��A�J�V���̂��ߎ��ۂɂ�11��̊J�ÂƂȂ�܂����B����ȊO�Ɏ����I�ɃE�C�[�N�f�[�̊J�Â���悵���̂ł����A�Q����]�l�����\�z�O�ɏ��Ȃ������̂Œ��~�Ƃ��܂����B��͂�A���Ȃ��Ƃ����サ�炭�͏T�����邢�͏j�Փ��ɊJ�Â��邱�ƂƂ������܂��B
����2���ԁA�_�u���X�ł̃Q�[�����s���Ă��܂��B�e��̎��{�͈ȉ��̒ʂ�ł������A���L���N��̊F���Q������A�܂������Ή��l�E���F�l�̎Q���������āA�y�������₩�ɃQ�[�����s���ǂ����������Ă��܂��B����͂��Ⴂ����̗��F����̊F���V�K�ɎQ������邱�Ƃ������o�[�ꓯ�傢�Ɋ��҂��Ă��܂��B�ܘ_�A�V�j�A�̊F����Ńe�j�X�ɋ������������̕��X�̎Q�����劽�}�ł��B���ЁA�����܂ł���������B
|
�� |
�J�Ó� |
�Q���l�� |
�J�Ïꏊ |
||
|
1 |
����26�N |
5��2�� |
�i���j |
6�� |
���c�J��呠���^���� |
|
2 |
�@ |
5��11�� |
�i���j |
5�� |
�����q�ː��X�|�[�c���� |
|
3 |
�@ |
6��29�� |
�i���j |
7�� |
���c�J��呠���^���� |
|
4 |
�@ |
8��24�� |
�i���j |
5�� |
�����q�ː��X�|�[�c���� |
|
5 |
�@ |
9��23�� |
�i�Ώj���j |
5�� |
���c�J��呠���^���� |
|
6 |
�@ |
9��28�� |
�i���j |
6�� |
�����q�ː��X�|�[�c���� |
|
7 |
�@ |
12��21�� |
�i���j |
6�� |
���c�J��呠���^���� |
|
8 |
����27�N |
1��12�� |
�i���j���j |
6�� |
���c�J��呠���^���� |
|
9 |
|
1��25�� |
�i���j |
4�� |
�����q�ː��X�|�[�c���� |
|
10 |
�@ |
2��7�� |
�i�y�j |
5�� |
�����q�ː��X�|�[�c���� |
|
11 |
�@ |
3��29�� |
�i���j |
6�� |
�����q�ː��X�|�[�c���� |
�ȏ�
�� ���ڂ�� �m�r�Q�P�`�r�Q�S���n�@�����F�M�c ���j�iS�Q�S���j�A��e �_�Y �i�r�Q�S���j
����26�N�x���ڂ��J�Õ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�����Q�U�N�x�̂��ڂ��́A���L�ɂ��e�r����J�Â��܂����B
�P�@�����@�����Q�U�N�P�P���S���i�j�P�P���S�O�����
�Q�@�ꏊ�@�L�������X�����@�����w��������X�e�[�V�����z�e���@�n�K�P�K
�R�@�Q�����@�V���i�Q�P�N���P���A�Q�Q�N���Q���A�Q�R�N���P���A�Q�S�N���R���j
�S�@�u����@�C�̃G�l���M�[�����p���悤�@���������{�̖����ׂ̈Ʉ����� �@
�@�@�u�t�@�v�c�v�v���@�@NPO�@�l�@�C���}���Q�P�@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�o���@�@���s��w�H�w�����A���^�A�ȍ`�p�ǁ@�`�p���������j�@
���{�́A�P�X�X�U�N�ɍ��A�C�m�@�����y���A�����Ɋ�Â��ĂP�Q�C���̗̊C�̊O�ɍL��Ȕr���I�o�ϐ���(ZEE)��ݒ肵���B����ɂQ�O�O�V�N�ɂ͊C�m�@�𐧒肵�A�C�m���ƂƂ��ĊC�m�����̊��p�Ɏ捞�ގ��Ƃ����B�ȉ��J���ߋ����q�ׂ�B
⑴ ���{�̊C�͖L�x�Ȏ����Ɍb�܂�Ă���B
���ӂ̊C�ɂ͖L�x�ȋ��ށE�C���ށE�H�������E�C��z���E�������ň��Ă���B
�C���E�g�́E���͓��̊��p�ɂ��G�l���M�[�͓d�͊��Z��2.1�`3.6��Kwh�Ƒz�肳���B���{��2004�N�̑����d�\�͂́A2.7��Kwh�ł���A���L�d�C�G�l���M�[��������̐��݃G�l���M�[�����݂��Ă���B
⑵ �J���ΏۊC��̒���
�C��ۈ����̃f�[�^�ɂ��A����k���C��A�g�J���A���������A���̖��A�O��ߊC���ŁA���ϊC�����x2�m�b�g�A�ő�l4.8�m�b�g�ł���B
�܂��C�����x�́A�C��E�G�߂ɂ��قȂ邪�A�\�w��25�x�A�C�ʉ�800m�t�߂�4�`5�x�ł���B
⑶ ���d�ݔ�
�C���𗘗p�������d�{�݂́A���[200���t�߂ɁA�C���̉��x���𗘗p�������d�ݔ��́A���[800�`1000���t�߂ɐݒu�܂��͌W������B
⑷ ���d�ʂ̐���
���d�ʂ͗����̂R��ɔ�Ⴗ��̂ŁA�C��ɂ�蔭�d�ʂ́A�傫���ϓ�����B�����^�őz�肵���������C��ł̔N�Ԕ��d�ʂ́A6�C34���������ŁA�N��18�����т̈�ʉƒ�̓d�͏���ʂɑ�������B
⑸ ���d�R�X�g
���ݔ�ƔN�Ԕ��d�ʂɎZ�茋�ʁA�����^��12�C4�~/kwh�`23�~/kwh�ł���A�V�����G�l���M�[���ƂƂ��Đ����̉\��������B�@�@
�T�@���e��
�@�@���ؗ������Ȃ���A�P��̊e�l����̋ߋ����s��ꂽ�B
�U�@��v
�@�@���F���̕⏕��20,000�~�Ɖ��P�l����4,000�~�Řd�����B
�V�@�����Q�V�N�x�v��
�@�@�����̉���̎Q����ڎw���āA10�����{�ɊJ�Â̗\��ł��B
�ȏ�
���܋㗌�� �m�r�Q�T�`�r�Q�X���n�@�����F���� �O�i�r�Q�V���j
����26�N�x�܋㗌��J�Õ�
1. ������
����26�N5��24���i�y�j�@NEC�N�������قɂā@�e�w�N����6���Q��
�@
�O�Q5�N�x����̈��p��������
�A
26�N�x�܋㗌��͍ŏI��ƂȂ�̂ŁA��ې[���^�c��ڎw���đ��k�����B
2. ��37��܋㗌���
����26�N9��27���i�y�j13�F00�`16�F00�@NEC�N�������قɂā@28��
�V���[�g�X�s�[�`
�e�[�}�F�@�d�q�����@�J���̎v���o
�u�t�@�F�@����@�O�@�@�iS27�N���j
�X�s�[�`�v�|�F
����NEC�ɓ��Ђ������̓N���X�o�����@�̊J���^�Œ��ł��������A���̐�͓d�q�������낤�Ƃ������ƂŁA�����O���[�v�������A�p�����g�������g���������@���������A�g�����W�X�^�_����H��p����PBX��������肵�Ă����B���̓�Bell System���ʘb�H�͋@�B�ړ_�����A���䕔���R���s���[�^�����ă\�t�g�E�F�A����Ƃ���v���I���������p�������B�@���{�ł�NTT�ʌ��𒆐S��NHOF����4�Ђ����������̐��̂���D-10�����@�����p�����S���I�ɓ������ꂽ�B���̌�d�q�����@�̗A�o�Ɩ��Ɍg��钆�œ`���ʐM�Z�p�Ŕ��W����PCM�����̌����ւ̊g���A�܂�f�W�^�������@�̊J�����K�R�I�ƂȂ����B����ɂ��f�W�^���ʐM�͈͉̔͂������瓮�摜�ʐM���܂ޒ������p�P�b�g�ʐM�ɓ�������d�b�����@�̓C���^�[�l�b�g�ʐM�ɗZ������A�p���������ƂɂȂ�B
�w�N����(S25)�R�c����Y�����A�����Ĉ��ނƌ��N���i�Ɍ����u���f�̗t�v�̐V�����������z�z���ꂽ�A�@�R�c����͍ŋ߂͖w�ǖ�����z���Ă��������{���ɗL��B���ӁI
���e��
�@�V���[�g�X�s�[�`��A����c�����ŗ��H�p�[�e�B���s�����B�A���R�[��������Ƌ��ɁA��ϕ��͋C������オ��A34�N37��̉�ő��ƔN���Ԃ̕ǂ��Ⴍ�Ȃ�Ō�̉��ɂ��ތ�荇���������ɓW�J���ꂽ�B�Ō�Ɋw�N�����o���ґS�����O�ɏo�Ĉ��A���A�ʂ��ɂ���ʼn������B
�ȏ�
���݂Ƃ����� �m�r�R�O�`�r�R�S���n�@ �����F��c�@����@�i�r�R�S���j
����26�N�x�݂Ƃ�����J�Õ�
�����Q�U�N�x�݂Ƃ������́A�X���P�V��(��)�P�P�F�O�O�`�P�S�F�O�O�ɍ��֘a���قŊJ�Â��A�R�P�����o�Ȃ����B
�`���@�J��A�ɉ����ē��Ԃ̂r�R�S�������A���̑���I�����Ȃ� �݂Ƃ���������U����|�����m�点�����B���̌�@�r�R�S�� �O�ց@�C�N�ɂ��u���u�R���s���[�^���̕���v���s��ꂽ���A�o�Ȏ҂ɂ͊֘A�����l�������A�����Ɖ����̏���������āA�D�]�����B�����ŁA��ꒆ��ɉ����ďo�ȎґS���̏W���ʐ^���B�e�����B���̎ʐ^�͌�����[���ŏo�Ȏ҂ɔz�z�����B
�@���ɉ���ɓ���Ɛ悸�ŔN���̂r�R�O�������A������V�W�`�W�Q�ƍ�����o�Ȏ҂������X���ł��铙�A���ʂ̎���ɂ���̌p��������ƂȂ����̂őS�w�N�������c�̂����A������I�����Ȃ� �݂Ƃ���������U���邱�ƂƂ����|�̌o�ܐ�������������A���t���o�āA������݂ɘa�C�\�X�̒k���d�˂��B
�@�Ō�Ɂu疗y�̉́v�Ɓu���i�Ύ��q�̉́v��S���ō������Đ���ɕ���B�@
�ȏ�
�����ɉ� �m�r�R�T�`�r�R�X���n�@�����F�@���� �O�i�r�R�U���j�@
����26�N�x���ɉ�J�Õ�
2014�N10��29���w�m��قɂ����ċ��ɉ�̏W�܂���J�Â��܂����B�{�N�x�́A���a36�N���̘a�c�������ɁA�u���ȏ�����������������`���{�̌Ñ�j�`�v�Ƒ肵�ču�������Ē����܂����B�הn�䍑�̋�B�������ȂǍŐV�̌����ɂ��ċ������邨�b���f���܂����B(�Q����20��)�@�u���I����̍��k��ł́A���N���̘b�肪�����Ȃ�܂����B
�@�܂��A�{��ł́A������݂̐e�r��}�邽�ߔN2��S���t���s���Ă��܂��B�{�N�͎��̒ʂ�s���܂����B
² 2014�N3��18��(��)�@�������J���g���[�N���u�@�Q��9��
�D���͌��V�v�(���a35�N��)
² 2015�N4��16��(��)�@���Ëv��J���g���[�N���u�@�Q��11��
�D���͌��V�v�(���a35�N��)���A�����Ċl��
�ȏ�
�������� �m�r�S�O�`�r�S�S���n�@�@�����F�X�c�@�_�O�iS�S�P���j
����26�N�x������J��
�����ȗ�6�N���o�߂���������́A41�N������x�ڂ̊������ԂƂȂ�A�����𐬂��������u�͂�Ԃ��v���n���Ɏ����A�����u�C�g�J���v�̔����q�̃v���W�F�N�g��JAXA�F�����̃����o�[�Ƃ��ĎQ�����Ă���41�N���̌��䂳��̂����b�ʼnF�����̌��w����悵�܂����B
�J�����F����26�N9��18���i�j�@15�F00�`20�F00
���w�ꏊ�FJAXA�F���Ȋw���������͌��L�����p�X 15�F00�`17�F30
���e���F�ؑ]�H�@���c�X 18�F00〜20�F00
�Q���Ґ��@�@25���@�@�@�@�@�i�F�������w����1���A���e���1���j
�F�����ł́u�͂�Ԃ�2�v�̑ł��グ��12���ɍT���Ē����Z�Ȓ��A�X�P�W���[�����]�O�]�Ƃ�肭�肵�āA���w���������A�����p�́u�C�g�J���v�̔����q����ʂɌ����Ă��炤���Ƃ��ł��܂����B
�����͈�J�������̂����A�Ɏn�܂�A�u�͂�Ԃ��v�v���W�F�N�g�̗��b�܂ŕ����Ă��̂���J�ɋ����ƂƂ��Ɂu�C�g�J���v�̔����q���������Ō��āA����Ȕ����q�͂��Đ��\���N�O�̑��z�n�̗��j�̏������o����Ȋw�Z�p�̐i���Ɋ������܂����B���̌�A�W����́u�͂�Ԃ�2�v�̎�����͌^�Ƀv���W�F�N�g�̐������F�O���ĉF��������ɂ��܂����B�Â��āA���c�̖ؑ]�H�Ɉړ����a�C���������ō��e��[�߁A���̒lj������ȂǁA�������n���n���������ʂ�����܂������A���Ƃ��\�Z���Ɏ��߁A���N�̍ĉ����ĎU��܂����B
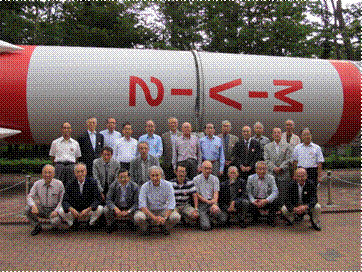
M-V�i�~���[ �t�@�C�u�j���P�b�g2���@�̑O��
�ȏ�
�����k�� �m�r�S�T�`�r�S�X���n�@�@�����F���R�@��i�r�S�V���j�A�@�r�@�a�v�i�r�S�W���j
����26�N�x���k��J��
���k��̍u����E���e����Q�U�N�P�Q���U���i�y�j�[���ɕi��Ŏ��{���܂����B�O��͉��l�݂ȂƂ݂炢�Ŏ��{���܂������A����͋��s��w�̓����I�t�B�X�i�i��j�ōu��������{���A�߂��̃��X�g�����ō��e������{���܂����B����̎Q���҂͂Q�V���ł����B
�u����ł́A���a�S�W�N���œ�����w��[�d�̓G�l���M�[�E���Z�p�����Z���^�[(APET)�ł�����Ă���J�����l��������u�X�}�[�g�O���b�h���Ƃ�܂��v���e�[�}��
�P�D
�n�����g���Ɗ����i��v����CO2�r�o�ʁA�d�͏���ʁA���d�d�͍\���j
�Q�D
�Đ��\�G�l���M�[�d���i���z���A���́A�o�C�I�}�X�A���z�M�A�n�M�A�������́A�����́A�g�́A�C���E�����Ȃǁj�̓����ƊJ�����p��
�R�D
���B�L���d�ł̕�����Ɖۑ�A����ѓ����{��k�Ў��̃C���t��������
�S�D
�����̓d�͋����V�X�e���Ƃ��ăX�}�[�g�O���b�h�i����ށA���l�s�A�L�c�s�A�k��B�s�ł̎��؎�����X�}�[�g���[�^�����v��Ȃǁj�̍ŐV��
���̋����[���u�������{���Ē����܂����B�u����I����͓����I�t�B�X�߂��̃��X�g�����ŁA���k������ɍv���������������x�����̉������l�̂����A�A�������x�����̈��c�L�l�̊��t�����e��[�߂܂����B
���e��̍Ō�ɂ͍P��̔��i�Ύ��q�̂�S45���̈��╟�M���܂̃n�[���j�J���t�����ƂɑS���ō������A�����x�����x�����̐��{����l�̈��A�Œ��߂�����܂����B�Ȃ��A����͕���27�N�Ăɍ��e��̊J�Â�\�肵�Ă��܂��B

�ȏ�
�����Ή� �m�r�T�O�`�r�T�S���n�@�@�����F�ɓ��@����iS�T�S���j
����26�N�x���Ή�J�Õ�
��N�ݗ����ꂽ����̗��Ή�i�r�T�O�`�r�T�S���̊g��N���X��j�̑�Q�����A�Q�O�P�T�N�R���P�W���P�X������w�m��قɉ����ė��H���k�ŊJ�Â��܂����B
�@���{���x�������܂߂ĂR�O���̎Q���āA��N�x�ݗ�����̈ɓ��l�i�r�T�R�N���j�̊��t�Ɏn�܂�A���k��A�Q���ґS������P�����x���ł����ߋ����܂����B�d���̘b����A�܂���̘b������A������������[�����e����ŁA���܂�ʎ��̂Ȃ��������̑��N�̕��X��m�邱�Ƃ��ł��A�w�N�Ԃ̋���������ɋ߂Â����������܂����B
�@�b��̓r��邱�ƂȂ����k���i�݁A�Ō�ɕ��x��������̎�����ւ̎Q���̂����߂Ȃǂ����A���A�����̐쌴��l�i�r�T�O�N���j�̒����߁A�L�O�B�e���s���A���N�x�̍ĉ��ĎU��܂����B�����Ƃ����Ԃ̂Q���Ԃł������A���̌�A�ʂɓ�Ɍ��������O���[�v������܂����B
�@���s���ɂ��Q���ł��Ȃ��������X���A����͂��ЁI

�@�@
�ȏ�